日本では最近,「連節バス+PTPS=BRT」という定義をしているのではないかと思われるが,やはり違和感がある.特定の目的地まで多くの客を運ばなければならないのなら,「長〜〜〜いバス」としての連節バスはありだとは思う.

他に写真がないので,ここばかり出てきて恐縮だが,特にここがどうということは無くて,これはこれでとにかく数を確保するという所期の目的は達していると思う.
忠節バシを連節バスが走るご時世か.
しかし,LRTのゴムタイヤ版交通機関として見ると,運転席横のいつもの「関所」は相変わらず存在しており,降車にやたらと時間がかかったり…

通行のプライオリティーが低くて,昭和40年前後の各都市の廃止直前の路面電車を思い出す風景にはやはり違和感がある.これは果たして最新鋭の都市交通か…といわれると,やはり違う.「長〜いバス」だ.

確かに,たくさん運ぶことができるようになると,交通計画の教科書では「中量輸送機関」の範疇に分類されるのだが,それを目的とした連節バスをBRTと呼ぶなら,それは本来の意味とは違う.もしそうなら,鉛直方向に積み上げたこれもBRTということになるけど,違うだろ?

「運行計画」タグアーカイブ
茨城県のBRT(ひたちBRT編)
日立にもBRTがあるようなので,立ち寄ってみた.日立駅ではなく,大甕(おおみか)駅発着.ここも日立電鉄線の廃止線路跡をバス専用道として活用している.廃止路線の代替バスというわけではないようである.



大甕駅から少し南下した地点から線路跡地転用の専用道路に入る.ここは一般道からの出入り口で,やはりバス側に遮断機がある.


このバスのおもしろい点は,整理券がICカード化されていることである.現金精算時の取りっぱぐれ防止策としては,世界一かもしれない(が,それでいいのか?).運営事業者が日立製作所グループだから,機器類のショーケースと理解すればいいのだろうか.

専用道路はさほど延長は長くないが,全線にわたって歩道が整備されているのでこの専用道にぶち当たりさえすれば,停留所にたどり着くのは容易である.地元住民のお散歩コースにもなっているようである.

停留所部分で行き違いが出来るようになっているほか,要所要所でも交換できるように道路が部分的に太くなっている.停留所は屋根付きだが,かなりシンプル.


歩行者用の「踏切」もある.

一般道との交差点については,バス道路側に遮断機があるのは「かしてつBRT」と同じ.信号機付きの場所もあれば,単に一旦停止の場所もある.

元日立電鉄の久慈浜駅で専用道は終了.ここから先は一般道を走る普通のバスである.

茨城県のBRT(かしてつBRT編)
2007年に廃止になった鹿島鉄道の代替バスは「かしてつバス」と呼ばれる.運行はかしてつではなく,関鉄グリーンバス.その路線の一部が鹿島鉄道線の路盤を転用したバス専用道になっており,「かしてつBRT」と呼ばれているらしいので行ってみた.
常磐線の石岡駅から出て,このあたりから専用道路に入る.

石岡南台駅.かつてのプラットホームを転用しているように見えるが,そうではなくて,左側はバス停標識が停留所本体.右側は屋根付き.


元の鹿島鉄道線時には使われていたであろう跨線橋とその下の駅舎(?)は,今は使われていない.ハードウェアは作る金があっても運営に手厚い保護をすることができないのが日本のシステム.

所々に道が太くなった行き違い箇所が有り,上下便が交換する.

一般道との交差部分は「踏切」が付いているが,専用道の優先通行を確保するというものではなく,一般道から誤って専用道に車両が進入しないようにするだけである.バスが近づくと遮断機が上がるが,バスそのものは原則一旦停止のようである.もっとも,交差する一般道の交通量が少ないので,このような交差点が遅延の原因にはならなさそう.


道路としては貧弱だが,便数も少ないので,さほど交換待ちも問題にはなってなさそう.並行する国道(下の2枚目)が,時間帯によっては渋滞するようで,それなりに効果はある模様.なお,運賃は普通のバスなみ.運行本数は残念ながら少ない.


ここで終点.

専用通路が確保され,定時性確保の努力がされているのは評価できるが,本数が少なくて1本逃すと待ち時間が長い.値段も安くは無く,海外のLRTのゴムタイヤ版だと思い込んではいけない別物である.廃止鉄道線の代替バスとするとまぁOKか.高頻度運転も,低廉な運賃も,中心市街地活性化も,P&Rも,信用乗車etc…もなく,これをBus「Rapid」Transitと呼ぶのは個人的には若干抵抗有り.
トラム変幻自在(観光トラム&バス編)
ウィーンに行くと,幸せの…かどうかは知らないが,黄色い観光専用トラムが走ってくる.RingTramと名付けられており,環状線をぐるぐる回る観光専用トラムである.車内で観光案内があるらしい.

このほかにも,観光用の工夫としては「HOP ON HOP OFF」というシステムがある.こういう停留所.

「HOP ON HOP OFF」専用停留所で待っていると,それ用のバス系統があり,専用切符を持っていれば自由に乗り降りできるというもの.

一般的には,観光バスには定期観光バスというシステムがあり,申し込んでおくと半日とか2-3時間で市内を案内してくれるバスツアーが一般的である.ところが,気に入ったところでも決められた時間しか滞在できないし,気に入らなくてもバスの出発を待たなくてはならない.(特に,海外でのこの手のツアーは要注意で,集合時間に遅れると,「あれ? その辺に座ってたメキシコ人のご家族知りませんかぁ? いないですねぇ.ここが気に入ったんでしょう.」とか何とかで,すぐに出発,という光景をカナダで見たことあり.)
「HOP ON HOP OFF」は一定時間毎にやってくる専用観光バスに乗りさえすれば,長時間滞在したければできるし,パスしたければ降りなければいい,ということができる.定期観光バスと公共交通の中間的なサービスである.
京都市内でも京阪バスが試行していたと思う.
日本に本物のBRTは出来るか?(優先信号)
フランスのナント市のLRT4号線ことBRTシステム「Busway」である.郊外方向に行くと,一般道の中央に専用レーンが設置されているところがある.ただし,見てのとおり,明らかに専用であることがわかるようなインフラである.視覚効果を狙ったものというよりは重量級のバスが通過することに対応して舗装が強化されているのではないかと思われる.分離帯が無いが,一般車の走る車線よりは若干路面そのものが高くなっているようである.
さて,写真は交差点部であり,鉄輪式のLRTと同じく赤青黄色の信号機とは別に縦棒横棒式の専用信号機が設置されているが,おもしろいのは交差する側の道路に対して「踏切警報器」があることだ.2枚の写真の違いがわかるだろうか? 縦に2灯並んだ赤色灯が交互に点滅している.ナントのBRTには踏切がある.つまり,BRT側が完全な優先権を持っているということであろう.それに比べて日本のPTPSは何と控えめなことか…


確かに,これほど確実な優先信号なら平均速度は高いだろう.これならBus Rapid Transitである.そういえば,日本の「BRT」ってどういう定義だったっけ?
LRTを使ってみよう(PARK & RIDE編)
LRTを使ってみよう(PARK & RIDE編)
新聞記事の精度(京都民報編-その2)
タブロイド紙の件の続きである.市の担当部局も噛みつかれているようである.
リニア新幹線は,予定では東京,名古屋,大阪の各都市に設置される駅は全列車の停車を想定した2面4線の駅構造(ホームが2面,各ホームの両側に線路が2線ずつの計4線という意味),それ以外は通過線2線+停車用線2線の計4線が想定されている.後者の駅については1時間あたり1本の停車を想定し,東-名-阪間の速達便が1時間あたり8本を想定している.噛みつかれているのはこの辺である.
リニア用車両は定員1000名程度とされているので,「それ以外」の構造になるであろうリニア京都駅では24時間ぶっ通しで運転しても1日2.4万人になり,市の計算の1日あたり3.3万人は処理できないではないか,というタブロイド紙の指摘である.
市は中間駅での実現は無理,と言っているようだが,そうなのかな? 例えば,東海道新幹線の場合は概ね3分弱-4分間隔程度で運転でき,毎時15本から17本以上運転できるようになっている.リニア新幹線については,実は現時点では最小運転間隔については公表されておらず,「毎時片道あたり8-9本しか運転できません」とも言っていない.車両基地が都心から離れた箇所に設置されることになっており,営業列車とは別に回送列車が品川-基地間などに走ることがわかっている.つまり,線路の能力そのものは「8-9本」より多いことは確かである.
リニア新幹線の最小運転間隔は公表されていないが,途中1駅停車の速達便が全線で67分,途中7駅停車の各駅停車型が全線で100分程度の所要時間であることが公表されている.速達型は平均7分半毎に運転されるので,各停型の所要時間が33分余分にかかっていることから,各駅停車型は速達型に33÷7.5=4.4回(平均)抜かれる.「中間駅」6駅中4.4回なので,停車すればかなりの率で追い抜かれるわけである.
在来線の場合は,普通列車と特急列車では使用車両が異なり,走行性能も大きく異なるが,新幹線の場合は東海道新幹線であってもリニア新幹線であっても,各停型と速達型とでは車両性能は違わない(同じものが使われる).ということは,ダイヤ編成上,速達型と次の速達型のダイヤの隙間には各停型の走れる隙間が常に確保されているということである.
| 各停リニア先発 | →→→ | 途中駅停車 | (空きダイヤ) | |
| 速達リニア次発 | →→→ | ↓ | →→→ | 速達リニア先着 |
| (空きダイヤ) | 途中駅発車 | →→→ | 各停リニア後着 |
各停型が4.4回抜かれるのなら,少なくとも「ダイヤの隙間」は+1本の5.4本分は隠されていることになる.5.4本分の隙間のうち,1本を各停型に,残りを回送列車用にという使い方であろうか.
8本の速達型用のダイヤと5.4本の回送/各停用ダイヤ,つまり,毎時13-14本以上,最小運転間隔は4分半程度未満というのが理論上の最大容量ではないだろうか.これはちょっと前の東海道新幹線の線路容量(運転可能な本数)である毎時15本とそう大きな差はない.
#論拠はそろってないが,最小運転間隔は3分45秒じゃないかな.3’45″×16=60’00″.16本の容量のうち8本を速達型に割り当て,その隙間の8本を各停型/回送に割り当てて,追い抜きされる場合は各停型が停車駅で「次の隙間」に移れるように全体のシステム設計をするとダイヤ編成は東海道新幹線のノウハウが活用できる.デジタルATC導入前の東海道新幹線は最小運転間隔は3分45秒だったと思う.
現在,東海道新幹線の「中間駅」ではこだま号もしくはひかり号の各駅停車型は毎時3本程度,旧式車両と旧式保安装置で走っていた国鉄末期でも各停型は毎時4本運転されており,これを参考にすると,毎時1本しか線路容量的に停車できない,ということは無さそうだと思われる.停車場設備の簡素なリニア「中間駅」の停車方法については鉄道の専門家からもいろんな提案がなされている.
あまり話題になっていないが,リニア新幹線は営業時間帯が長い可能性が高い.東海道新幹線よりも1-1.5時間時間短縮されるので,その分終電の時間が遅くなるはず.6-23時の17時間,上の考察を参考に毎時4本停車,1000人のうち半分だけ降車と想定すると,計3.4万人になり,概ね計算が合うんだが.不可能で無い限り,客がいれば鉄道会社はそれに応じて停車させるのが基本であろう.
- ということで,毎時1本なのにおかしい,と噛みつくほどの話では無さそうである.
#まだ1面.

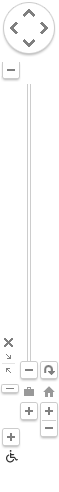














 Views Today : 140
Views Today : 140 Views Last 7 days : 3214
Views Last 7 days : 3214 Views Last 30 days : 12337
Views Last 30 days : 12337