九州新幹線の脱線現場は…さすがに手持ちの写真はないが,この写真のすぐその先,駅の南側の目と鼻の先のようだ.
九州新幹線全線開業 祝!九州縦断ウェーブ CMの,「祝!熊本」のテロップが出る少し前,小さなお堂の前の川沿いで人々が手を振り,旗と風車を持ったこども達が列車と併走するあたりのようだ.(3分版の1:02あたりから)

J-SHISという地震リスクの計算結果を地図上で確認できるサイトを見てみると,熊本市およびその周辺自体が九州の中では比較的地震のリスクが高かった地域のようだ.
使い方は基本的には検索サイトなどで提供されている地図の閲覧サービスと同じなので,拡大してみると熊本駅のある地域とその南側とでは地震のリスクの段階が異なっており,南にゆくほどリスクが高そうだ.
サイトの画面の上の方に表示させる条件がいろいろ変えられるようになっているので変えてみると,概して熊本城とその周辺の城下町あたりは地震リスク低め,熊本駅はそれに比べるとややリスク高め,新幹線の線路に沿って南下すると,白川や緑川といった河川流域はかなりリスク高め.河川で運ばれてきた堆積物で出来た平野のようである.
わずか1分ほどの走行らしいが,その列車位置の差が原因で脱線してしまったのかもしれない.地盤は大事.駅の位置の選定や路線の位置の選定も大事,ということかな.
#なお,首都圏や京阪神圏あるいは太平洋岸などでは,今回の脱線現場と同程度の地震リスクの箇所をかなり長距離にわたって新幹線の線路が走っている.



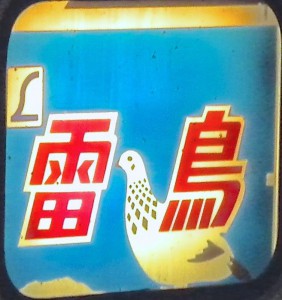





















 Views Today : 239
Views Today : 239 Views Last 7 days : 3234
Views Last 7 days : 3234 Views Last 30 days : 14299
Views Last 30 days : 14299