JR東系のデジタルATCは,「ボクにぶつからないように,●●●までに止まってね」と後ろの電車にメッセージを送る.
JR海系のデジタルATCは,「ボクは×××あたりを走ってるので,ぶつからないようにしてね.どこで止まるかは自分で考えてね.」と後ろの電車にメッセージを送る.
通常の使い方だと優劣はさほど無いように見えるが,将来的な高密度運転には後者の方が優位かな.
この流儀の差は微妙なものだが,少なくとも一旦立ち止まって頭を切り換えれば混乱は無い.走りながら,しかも安全側で判断しながら,両方の流儀に対応するのは少々面倒そう.車両側についてはある地点を境に判断基準を切り替えればいい.
だが,後ろの電車に送るメッセージは変換しないといけない場合がある.「ボクにぶつからないように,●●●までに止まってね」は,「●●● = ×××」と単純変換すれば「ボクは×××あたりを走ってるので,ぶつからないようにしてね.どこで止まるかは自分で考えてね.」とは(効率はともかく安全側の判断で)簡単に整合がとれる.
ところが,「ボクは×××あたりを走ってるので,ぶつからないようにしてね.どこで止まるかは自分で考えてね.」というメッセージについては,「××× = ●●●」と単純変換するだけだと「ボクにぶつからないように,●●●までに止まってね」と解釈すると前の新幹線に追い付いてぶつかってしまうかもしれない.なので,後続電車の性能を地上に教えた上で適切な停止位置を地上で計算した上で新たに「●●●」の位置を後続電車に教える必要がありそう.
…というふうに,異なる2つのデジタルATCを走りながら切り替える際の課題の対象法を考えてみたりして.


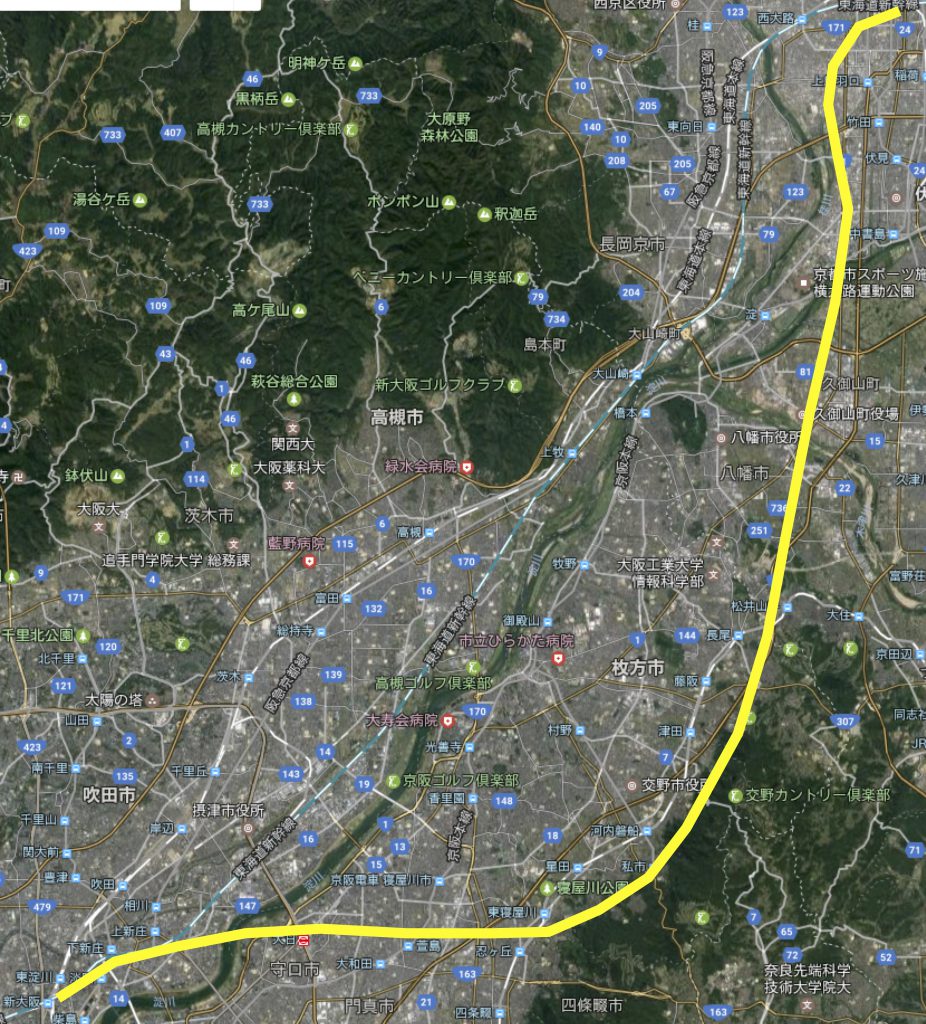






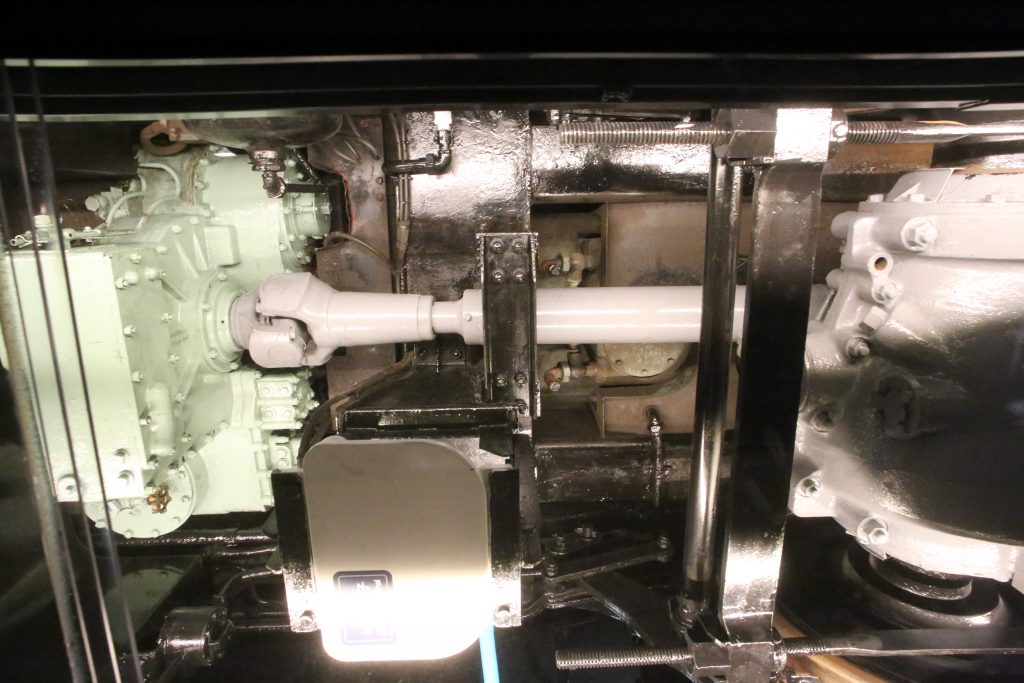




 Views Today : 118
Views Today : 118 Views Last 7 days : 2780
Views Last 7 days : 2780 Views Last 30 days : 12454
Views Last 30 days : 12454