島根の一畑電車.残念ながら本数は多くない.路線網は,松江と出雲大社を結ぶ路線と途中駅からJR出雲市駅へ伸びる枝線とからなる.松江から出雲大社に行きたい人もいれば,JR駅から出雲大社に行きたい人もいる.JR駅から松江方面に行きたい人もいる.ということで,ちょっと悩ましい.
出雲市駅から分岐駅の川跡まではこの電車.内装が独特である.奧のピンクの電車も他の追随を許さない.車両の話はまた後日.
出発して数分で速くも終点の川跡駅.前方に出雲大社方面からやってきた電車が川跡駅に侵入しようとしているのが見える.
そして,向こう側の松江方面からも電車がやってきた.
そして,川跡駅で全方向乗り換えOK.少ない便数ながら,最大の効果.
ダイヤ編成上のポイントは,乗り継ぎ駅に同時刻に全方向から電車が集まってくるようにダイヤを組むこと.これなら参考にできる地方鉄道線も多いはず.
























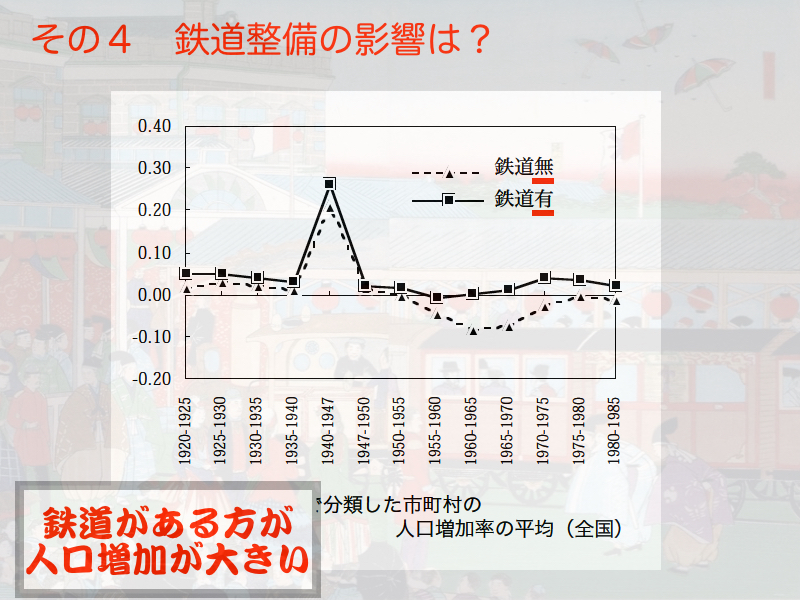
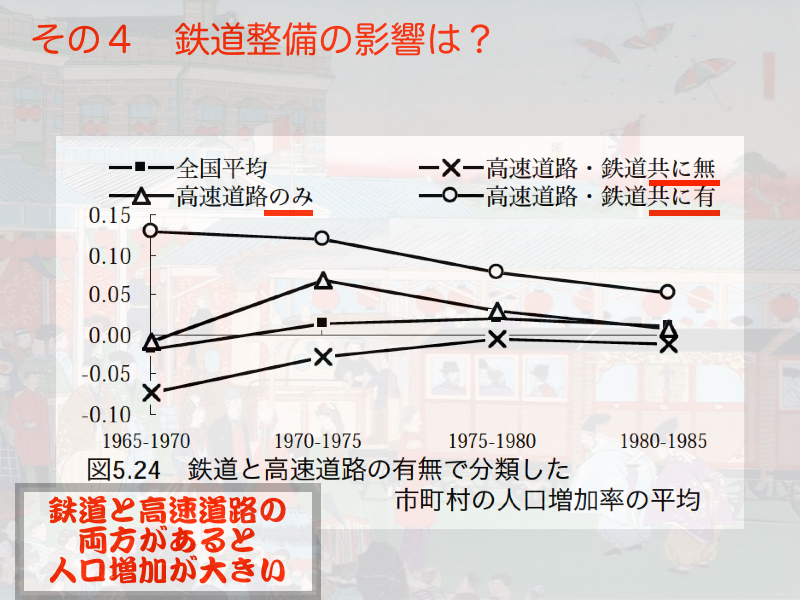





 Views Today : 412
Views Today : 412 Views Last 7 days : 2272
Views Last 7 days : 2272 Views Last 30 days : 12131
Views Last 30 days : 12131