大都市から離れると,線路際でよくこういったスローガンを見かける.
日本全国で複線化や電化を目指している鉄道線は多い.
じゃぁ,(米国はダメダメだが)欧州はというと,余程でない限りローカル線であっても複線化や電化はほぼ実現されている.少なくとも特急や急行相当の列車が走っているようなところで単線非電化にはお目にかかったことが無い.
この差はどこから来るかというと,ほぼ「カネ」である.ちゃんと財源が確保されているということ.日本でいうところのガソリン税相当の税金がちゃんと公共交通に還元されており,ローカル線の複線化・電化・路線改良・新車購入といったインフラ投資にまわっているのはもちろんのこと,日々の運営費にも資金が投入されている.
一方,日本ではガソリン税は「自動車ユーザー」という名のニアリーイコール国民の利用する道路投資にまわされていた.その道路すら,今や一般会計を通して投資されるようになり,ガソリン税は単なる普通の税金になってしまった.
インフラ投資しないと,後々困るぞ.いつまでも使えると思うな,何とやら.
なお,JRに期待する声は多いが,近年JR各社が自ら進んでローカル線に単独投資した事例はほとんどない模様.


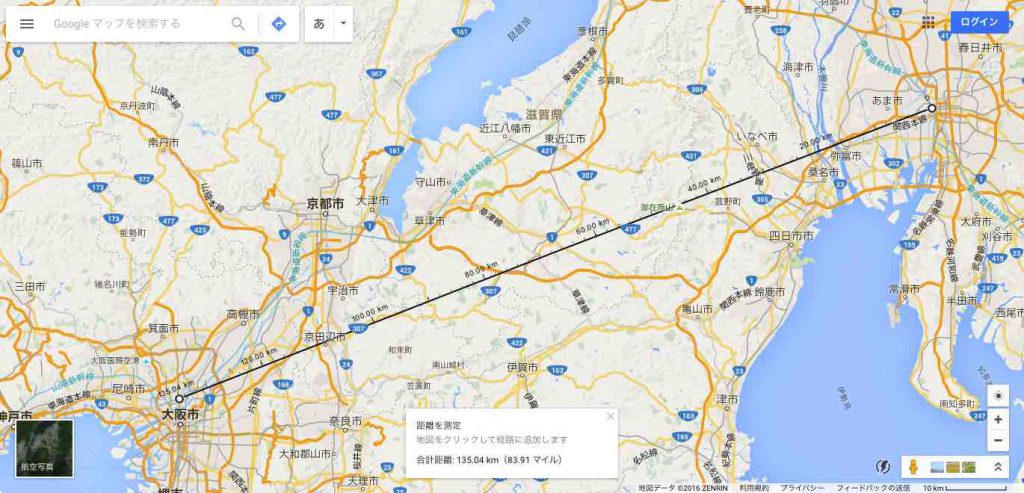
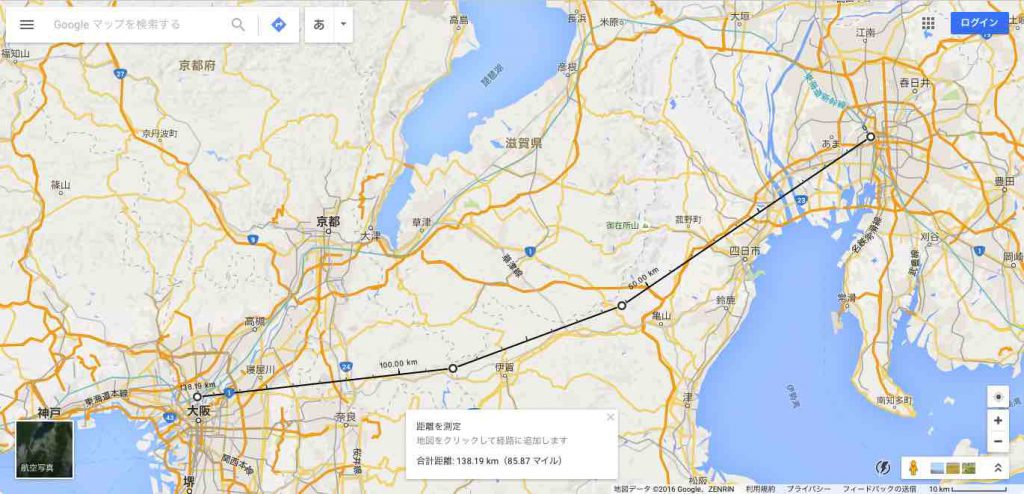
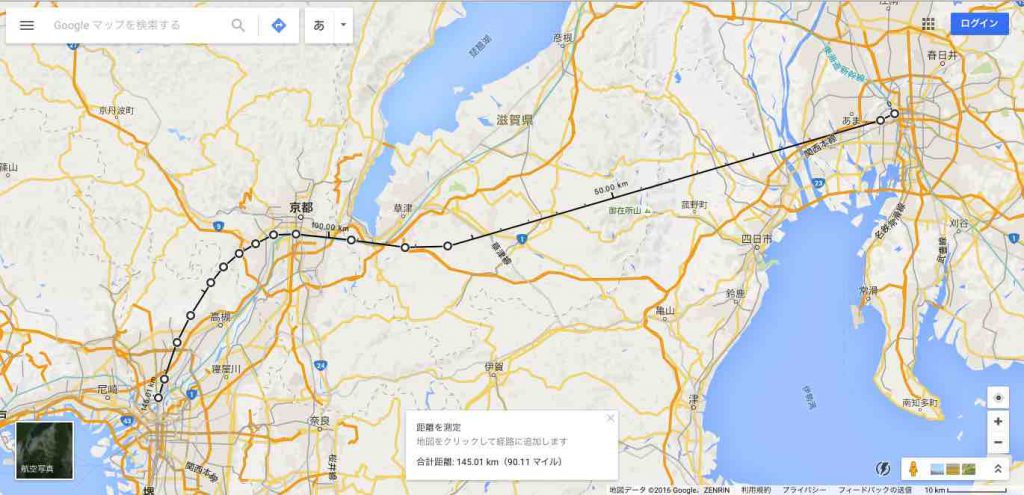
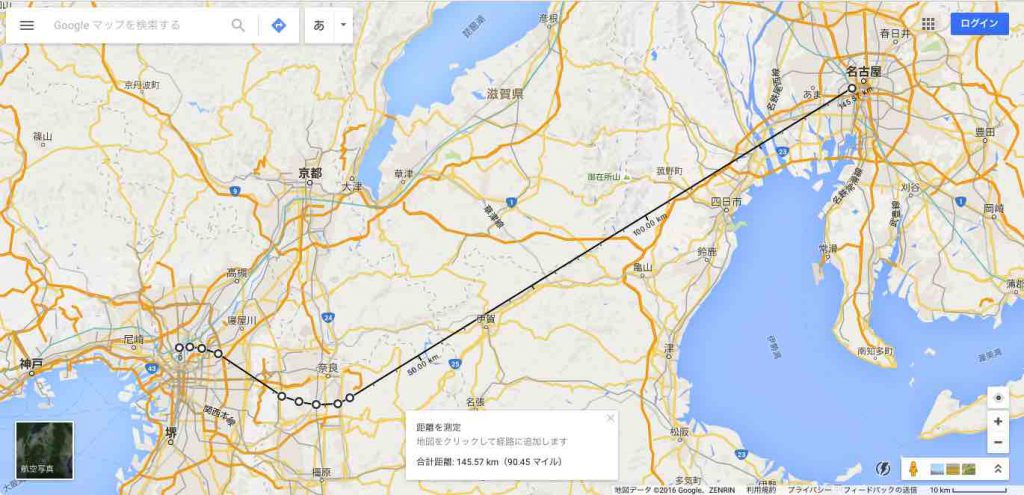
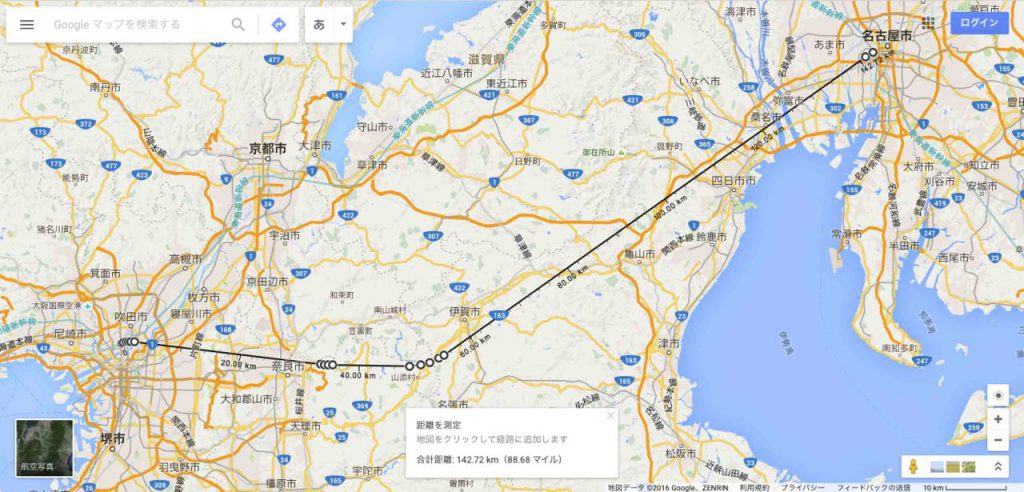






















 Views Today : 310
Views Today : 310 Views Last 7 days : 2806
Views Last 7 days : 2806 Views Last 30 days : 12439
Views Last 30 days : 12439