このお話.
北陸新幹線の大阪延伸をめぐり、京都-新大阪間で検討されている南北の新ルート2案のうち、関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)を通る「南側ルート」について与党…
情報源: 北陸新幹線「京都―新大阪」間に“第3のルート” 知事の意向受け奈良回避、与党が国土交通省へ検討要請
これまでの整備新幹線沿線各地と比べて負担額そのものは大したことが無いが,(今さら言っても遅いけど)リニアに気を取られて奈良が失ったかもしれない将来のポジションのお話.逃した魚は超デカい.
記事では北陸新幹線の南側ルートを打診して『けいはんな学研都市経由では多くの利用者が期待できず「財政負担に見合うメリットがない」と述べた。』とある.どこに駅をつくる想定で打診したのかは定かではないが,//奈良市やその周辺にとって便利な位置に駅をつくってくれ//…と,近隣のどこかの駅に併設させるような交渉をする価値はあったかもしれない.
ご存じのように,中央新幹線が奈良市付近を通過することが決まっている.これは東海道新幹線の代替バージョンアップ路線.北陸新幹線が奈良市付近にきた場合は,これは北陸本線(&湖西線)の代替バージョンアップ路線.構想レベルだが北陸新幹線は山陰新幹線と京阪間の線路を共用する可能性がある.これは山陰本線の代替バージョンアップ路線.
さらに,北陸新幹線が新大阪に達すると,現状の新幹線電車そのものでは難しいが山陽新幹線が京都あたりまで乗り入れてくる可能性は十分ある.というかJR西はずいぶん前からそれを希望していたと思う.つまり山陽新幹線も手に入れる.さらにさらに,北陸新幹線を新大阪経由で関空方面へと直通させるという構想もある.これは特急はるかの代替バージョンアップ.
つまり,上に書いた交渉をしていれば,ほぼ現状の京都市のポジションを手に入れることができた.東海道山陽新幹線だけでなく,国際空港アクセスや日本海側への高速アクセスが可能なポジションである.リニアの分だけ優位なので,100年くらいすると京都市と奈良市の全国的な地位が入れ替わったかもしれないのだ.だが,どうやらそこまでは考えが及ばなかったようである.
千載一遇のチャンスを逃したお話.
この結果,奈良がどうなったかについては,概ね100年後の2100年頃の歴史家がまとめてくれると思う.先見の明って大事だね.
#なお,リニアだけの状態だと「東京まで1時間半,名古屋まで30分ほど,所属する大都市圏の中心部まで1時間ほど,それ以外は特筆すべきもの無し」なので,全国的には豊橋市程度のポジションかな.都市規模的にも同程度だ.



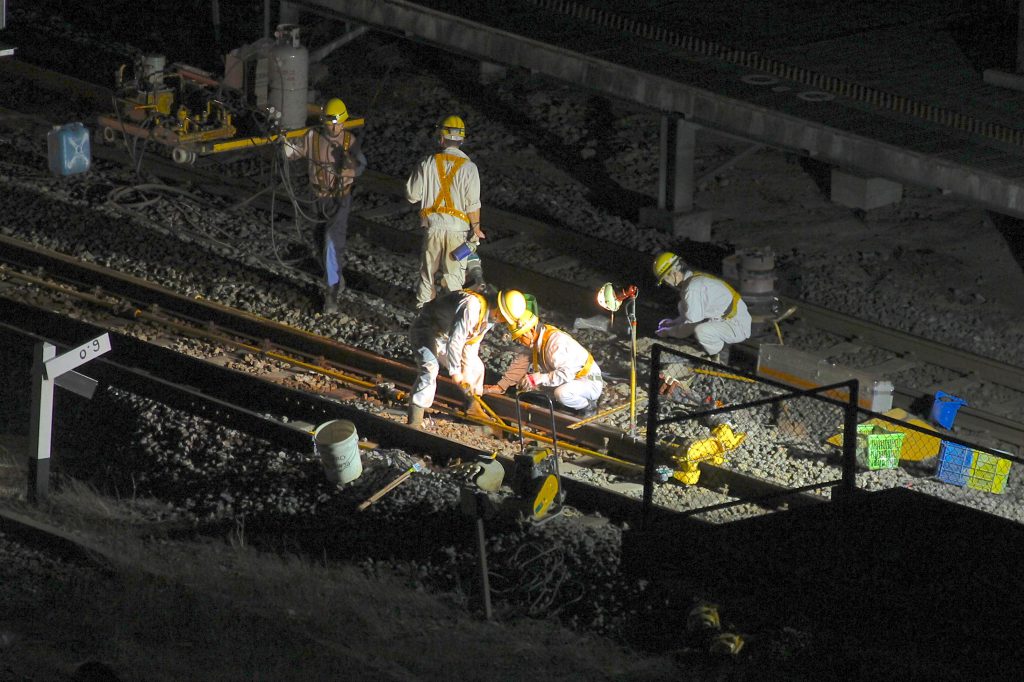






 Views Today : 203
Views Today : 203 Views Last 7 days : 2865
Views Last 7 days : 2865 Views Last 30 days : 12539
Views Last 30 days : 12539