最近,自動車に自動ブレーキ装置が搭載されることが多くなってきたが,これと同じものを路面電車に登載すれば,自動車と同じく事故を減らせるはず.
とすると,”歩行者との事故が心配”なトランジットモールについても,事故の心配が無くなるわけで,課題解決となるかも.
自動ブレーキ装置の搭載を条件に,トランジットモールを正式に認めても良いのでは?

関西本線に乗っていると,大阪府と奈良県の府県境あたりで大和川を北側から南側へ,そして再び南側から北側へと横切る箇所がある.
二度も鉄橋を渡らなくても,そのままトンネルでも掘れば良いのに,と思うような箇所だ.
通称亀の瀬という地区である.
元々は鉄橋で二度も川を渡ることなく,大和川の北側(右岸)をトンネルで通過していたが,ここは有名な地滑り地帯であり,トンネルは地滑りとともに破壊されてしまった.
そんなわけで二度も川を渡って地滑り地帯を避けている.
よく北陸新幹線は東海道新幹線に乗り入れできない,という.
その理由は,東海道新幹線が過密だから,東海道新幹線と北陸新幹線のシステムをつなぐには費用がかかるから,だという.
でも,誰も当事者に聞かないのね.
東海道新幹線は片道いったい何本の列車を通す能力があって,今何本の列車がとっていて,どの区間に空きは何本分あるのですか?
とか,
東海道新幹線は何分ごとに列車が運転できて,今何本走っていて,何本分空いているのですか.
とか,
「東海道山陽新幹線」と「北陸新幹線」のシステムを接続するには何億円かかるのですか?
とか,
「東海道山陽新幹線」と「北陸新幹線」を米原で接続する場合のシステム改修費用と,京都駅で接続する場合のシステム改修費用と,新大阪駅でで接続する場合のシステム改修費用は,それぞれ何億円なんですか?
とか,
米原で接続するのが高くて東海道山陽新幹線と北陸新幹線を直通運転できないのなら,新大阪で東海道山陽新幹線と北陸新幹線を直通運転するのも費用が高くてできないんですよね.
とか.w
近年,大阪では梅田貨物駅跡地がまとまった土地として注目され,その開発の動向が注目されている.いわゆるウメキタ.
物販オフィスホテルインキュベータ等々いろんな整備がなされつつあり,大阪市の重心は梅田地区に移動しつつある.
梅田貨物線を走っていたのは「はるか」や「くろしお」などであったが,晴れてウメキタにも駅ができて,大阪外環状線(おおさか東線)の電車がそこまでやってくるかもしれない.
新幹線も新大阪じゃなくて,ウメキタに引き込めという意見もある.まぁ,平時ならなんの問題もない.
ところが,平時ではない事態を考えると,あまりこういった北部集中は手放しでは喜べない.
以前指摘したように,もしも全国的な新幹線ネットワークが原案どおり完成し,地図のとおりになった暁には,「新大阪駅」が一番のネックになる.ここが災害テロその他理由で使えなくなると,完全に東西間広域交通が分断される.
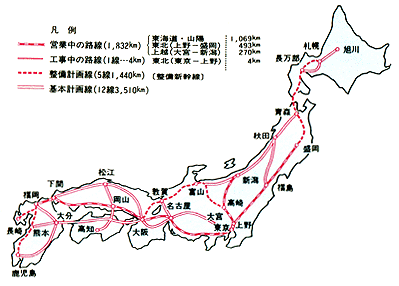
北部集中の弊害はそれだけではない.梅田地区は以前から大規模な津波に襲われた場合,浸水の可能性が指摘されている.新大阪も浸水が迫る.リンク先の図は大阪府の試算結果であるが,左上が新大阪駅,左中〜下が梅田地区である.いずれも安心とは言えない.その南も四つ橋筋よりも西は安全ではない.
えっ! 高層ビルに逃げ込めば大丈夫だって?
甘い甘い.大阪のような大都市は地下利用が広がっており,止水するとは思うが,一滴漏らさずに止水するのは難しいだろう.京都の京阪電車も大阪のJR東西線も(開業までだが)大雨で水没したことがある.
それから,大都市は「電気なければ,タダのハコ」(…歳がバレる)状態である.電気の変電所がどこにあるか考えたことがあるだろうか.Googlemapで大阪市の中心部を表示させて置いて「関西電力 変電所」で検索してストリートビューや航空写真を見てみると面白い.変電所の場所として指し示されるのは,たいていビルである.つまりビルの地下.地上の変電所建屋が示されることもあるが,引き込まれているはずの超高圧電線も見えなければ鉄塔も見えない.電線はどこ?
大阪市内のメインストリートでは,街路に電柱がないところもある.ここも電線はどこか? 地下である.
地下変電所や地下埋設電力線に津波の塩水が流れ込んだらどうなるだろうか.ちなみに塩水は良導体である.
通信線も地下埋設されているよね.
とかく開発は平時に注目が行きがちであるが,異常時にも気を配ることができるかどうかで本当に良い開発計画が定まるのではないかと思う.
大阪の都市計画プランナーのセンスは,秀吉や徳川を超えられるか?
#なお,京橋周辺も危ない.
ここ何日間か,観光バスの事故が頻発…
…しているように見えるんだが,おそらく碓氷峠の15人の犠牲者を出した事故を受けてマスコミが事故を積極的に報道しているだけなんだろうと思う.
大事故があって,バス会社各社は体制を引き締めて運行している真っ最中だろうと思うので,普段はもっと多いんじゃないだろうか.
先般の事故の犠牲者を見ると,若い人が多い.つまりあまり移動に費用をかけられない客層だ.夜間移動すれば宿泊費も節約できる.
かつては夜行列車がたくさんあって,特急ではない便も結構あった.夜間列車を走らせるには費用がかかるという話はよく聞くが,夜行貨物列車が走っているような路線では,昼間走っている電車そのままでも良いので,できないことも無いんじゃないかとも思う.バスよりはかなり安全だ.
あるいは,夜遅めに新幹線を出発させて,途中のどこかで長時間停車させて夜明けとともに運行再開するという方式も,昔からよく言われているが,そろそろ実行に移してもいいんじゃないだろうか.
そりゃぁ,無理ですよセンセ.費用と手間が…保守が…という話が聞こえてくるのは承知だが,鉄道における夜間移動サービスの提供は,ちょっとは考えてもいいんじゃないだろうか.
鉄道会社はサービス内容を単純化して利益を効率よく得ること以外にも,様々なニーズに対して様々なサービスを提供することをもっと考えてもいいと思う.それも一つの社会的役割だ.
前々回は副首都の立地場所として,平常時における大阪は悪くないという話であった.前回はまとまった土地がどこにあるかの話であった.
今回は,大阪市および前回取り上げた地区の地震動の話である.副首都は地域振興策では無く,非常時—特に首都直下地震や南海トラフ地震—におけるバックアップ機能を果たすことが期待されるため,地震で機能停止するような場所には設けられない.首都直下地震と南海トラフ地震は事実上連動する可能性もあるので,東京以外ならOKというものでもない.首都が機能停止している間に南海トラフ地震が襲うという最悪シナリオであっても対応できるのが副首都の要件である.
さて,以前にも参照したこのファイルを見ながら話をしよう.昨今の建築・建設技術等の発達に伴い,震度5台では大きな都市災害は起こらなくなってきているので,震度6弱以上あるいは震度6強以上で見てみよう.詳しい震度については,こちらのサイトの方が便利かもしれない.
まずは大阪府下である.
【大阪市中心部&夢洲】
震度6弱以上で見ると,ほとんど真っ赤(30年以内確率26%以上),つまり大阪市の中心部には逃げ場が無い状態である.夢洲も同様.震度6強以上だと,地下鉄堺筋線と谷町線附近の南北に長い地域—すなわち上町台地が若干マシで30年以内確率3%以下になっている.つまり,大阪市内は対地震の観点では非常に心配だが,敢えて言えば上町台地がマシ,ということである.上町台地の庁舎を放棄して府庁を埋め立て地に,というのは災害リスクの観点では論外ということ.なお,30年以内に3%の確率で震度7に見舞われる地区は大阪市内では京橋駅北方や住之江区の一部のようであり,このへんは特に避けた方がよさそう.
【伊丹空港付近】
地震に関しては概ね大阪市内の上町台地と同程度のようである.ただし,大阪空港の西側の猪名川に近いあたりは大きな震度に遭遇する確率が高めのようであるので要注意.中国豊中インター付近も地震リスク高め.
【万博記念公園付近】
ここは伊丹空港付近に比べて,さらに半段〜一段,地震リスクが低くなる.震度6弱以上では伊丹空港付近と同程度だが,震度6強以上だと色が1段薄い.他の視点での結果も同様の傾向だ.
【陸上自衛隊信太山演習場附近】
ここは,地震のリスクに関しては万博記念公園付近と伊丹空港付近との中間的な度合いのようである.大阪市内よりはマシだが,決定的にリスクが低いわけでは無い.
…ということで,大阪市内は論外として,府下では万博記念公園あたりが無難そうに見える.続いて大阪府以外についてである.
【巨椋池跡地附近】
なんとなく予想はしていたが,大阪市内と同レベルの地震リスクである.上町台地の方がマシ.沼地の干拓地であるので,足下はズブズブということだろう.堆積物が厚く層をなしているのかもしれない.ここは開発はしやすそうだが,対災害を考えると重要拠点には向いていなさそう.
【陸上自衛隊祝園分屯地附近】
ここは万博記念公園と同程度のリスクのように見える.ただし,分屯地を超えて開発する場合は要注意で,東側の木津川方向は地震のリスクが急に大きくなる.逆に西側の京阪奈丘陵の地震リスクは大阪付近の開発可能な地域の中では低い部類である.
【陸上自衛隊長池演習場附近】
ここは祝園分屯地よりもさらに若干ではあるが地震リスクが低そう.京阪奈丘陵と同程度だろうか.
…ということで,大阪付近でまとまった土地があり,なおかつ地震のリスクが低めのところを探すと,万博記念公園付近か陸上自衛隊祝園分屯地附近の京阪奈丘陵,あるいは陸上自衛隊長池演習場附近あたりということになる.
TGVが脱線したみたいなんだが…
ドイツとの国境に近いフランス東部ストラスブールの近郊で14日、試験走行中の高速鉄道TGVの車両が脱線し、少なくとも10人が死亡、37人が負傷した。AFP通信などが報じた。 技術者ら49人が乗車し、時…
他の写真などでは複線の上下線間が開いているようなので,LGVと在来線の合流点付近のようだ.水路をまたいでいるので,ここかな.
Metz方面からきたLGVの終点で,比較的急曲線で在来線と合流するあたりのようであり,地図上で見る限り半径800-1000mくらいの曲線のようである.標準軌なので,制限速度としては120〜150キロくらいだろうか.
高速新線を試運転して,そのまま減速せずに突っ込んだ感じだろうな.高速道路を快走していて,いきなり巨大な「終点」の看板が出てきたような感じか.
まだ営業していない新線のようなので,保安装置がまだ機能していなかったのかもしれない.TGVは新線が開通するのにあわせて高速走行実験をすることがあるので,そういった試験の最中の事故だったのかもしれない.
高速線と在来線の境目での事故という点では2013年のスペインのAVEの事故と似ている.また,直線を高速で走行した直後に急カーブが配置されていて脱線した,という点では福知山線の事故とも共通性がある.
高速鉄道では目視で危険を察知しても危険回避が間に合わないらしいので,保安装置は大事だということだね.