日立にもBRTがあるようなので,立ち寄ってみた.日立駅ではなく,大甕(おおみか)駅発着.ここも日立電鉄線の廃止線路跡をバス専用道として活用している.廃止路線の代替バスというわけではないようである.



大甕駅から少し南下した地点から線路跡地転用の専用道路に入る.ここは一般道からの出入り口で,やはりバス側に遮断機がある.


このバスのおもしろい点は,整理券がICカード化されていることである.現金精算時の取りっぱぐれ防止策としては,世界一かもしれない(が,それでいいのか?).運営事業者が日立製作所グループだから,機器類のショーケースと理解すればいいのだろうか.

専用道路はさほど延長は長くないが,全線にわたって歩道が整備されているのでこの専用道にぶち当たりさえすれば,停留所にたどり着くのは容易である.地元住民のお散歩コースにもなっているようである.

停留所部分で行き違いが出来るようになっているほか,要所要所でも交換できるように道路が部分的に太くなっている.停留所は屋根付きだが,かなりシンプル.


歩行者用の「踏切」もある.

一般道との交差点については,バス道路側に遮断機があるのは「かしてつBRT」と同じ.信号機付きの場所もあれば,単に一旦停止の場所もある.

元日立電鉄の久慈浜駅で専用道は終了.ここから先は一般道を走る普通のバスである.


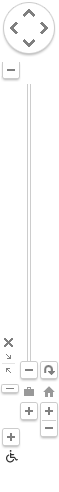



























 Views Today : 126
Views Today : 126 Views Last 7 days : 2827
Views Last 7 days : 2827 Views Last 30 days : 11976
Views Last 30 days : 11976