もうすでに指摘が出ているようだが,北陸新幹線用の長野の車両基地のロケーションが災害に対して脆弱すぎる.長野市の洪水ハザードマップによると,10-20mの浸水の可能性が指摘されているような地区(リンク先pdfのほぼ中央の「浅川」付近)であり,新幹線路線の川側は氾濫で家屋倒壊の可能性が示されている地区のようだ.長野市内でも最悪クラスの地区のようだ.
https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/330477.pdf
車両基地は平らな大面積の土地が必要なので,市街地の外側の水田地帯や埋め立て地などに立地しやすい.この車両基地も水田地帯に立地している.水田は水が必要なので,水を得やすい土地であるのは当然だが,逆に言えば水がやってきやすくて水はけが悪い土地でもある.
いちおう,ちょっとだけ盛り土しているようだが,浸水予想に比べて低すぎた模様.長野オリンピック対応で突貫工事だった影響か? 工事をしていた1990年代半ばはまだ浸水予想のハザードマップが自治体ごとにつくられるような時代ではなかったかも.とはいえ,市町村ごとにハザードマップがつくられるようになった昨今では,何らかの対策は考えておく必要があったかもしれない.
この付近では千曲川は北方に流れており川幅は900mほど.5キロほど新潟方面(下流)に行ったところで川幅が250mほどにまで狭まるので,千曲川の車両基地付近には高水時に水がたまりやすかったのではないかという専門家の指摘もあるようだ.
威勢のいい政治家の中には,こういった地域が水没するという犠牲によって川下の都市が守られており不公平だ.そういう議論を情報公開請求によって白日の下にさらすべきだ,などと叫ぶ人がいるようだが,山と山に挟まれた谷を平地部と同じ川幅に広げ,さらに淀川のような真っ直ぐな流路にするには大幅に地形を変更する必要があり,限界はある.「トロッコ問題」の河川版を想定しているのかもしれないが,もしそうならば “何も治水せずに全くの自然に任せる” というのがその脳内シミュレーションの答えになるので,政治の基本が機能しなくなる(治水は政治の基本中の基本).
#治水計画は下流から上流まであるが,上流から工事を開始すると流れが良くなってやってスイスイ流れ下ってきた水が下流で氾濫を起こすので,下流から工事を開始して流れを良くしておいてから上流の工事に入るのが手順だと思う.問題は,治水工事費用を無駄だという輩が時々いるので,上流までの工事がなかなか完了しないということ.「上流は死んでしまえ」と治水計画に書いているわけではないと思う.
それから,ボトルネックを解消すると別のボトルネックが顕在化することは常なので,そのへんのシミュレーションは専門家に任せるべし.たぶん,5キロほど下流部分のさらに下流の中野市では流路がくねくねしており,三日月湖の跡まであるので河床勾配が緩く,水がたまりやすい地区だと思う.ボトルネックが下流に移るだけだな.トロッコの軌道を切り替えたらその先にも人がいる状態だ.
さらにその下流を広げると,今度は飯山市が似たような状態だ.さらにその下流を広げるには,日本地図でもわかるくらい派手に長野県北方の山々を消し飛ばす必要ありそう.消し飛ばして川幅を広げるとその下流は新潟県津南町になるが,ここは今回の水害でも被災地域のようなので,結局完全解決にはならない.ということで,ええい,もう日本海を長野の近くまで掘り込んでしまえ…という感じか?
この車両基地は応急の復旧が終わったら,何らかの改善策が練られることだろうし,千曲川の治水対策も改善されるだろう.
さてさて,ほかの新幹線車両基地はどんな立地だろうか.いくつか見てみよう.
まずは,北陸新幹線の白山車両基地.ここも田んぼの真ん中につくられている.だが,少しだけ盛り土されているようだ.
東海道新幹線の名古屋の車両基地は庄内川の川沿いにある.ここも少し盛り土されているようだ.
ところが,危なっかしい車両基地も存在する.大阪の鳥飼基地(東海道山陽新幹線)は神崎川の支流と淀川に挟まれており,しかも平地だ.かつてはあわや水害という危機が迫った際に車庫の電車を盛り土の本線上に待避させてしのいだ話は比較的有名だ.
岡山の車輌基地も平地で,田んぼ地帯だ.九州新幹線の熊本の車両基地は田んぼの中の立地で盛り土無しだ.鹿児島の川内の基地は田んぼの中だが盛り土されている.
ということで,大丈夫そうな車両基地もあるが危なそうな車両基地もあるというのが実情の模様.盛り土し直すのも難しいかもしれないので,この際,他の車両基地では「電車水没回避マニュアル」でもつくって,時々予行演習しておいた方がいいかも.

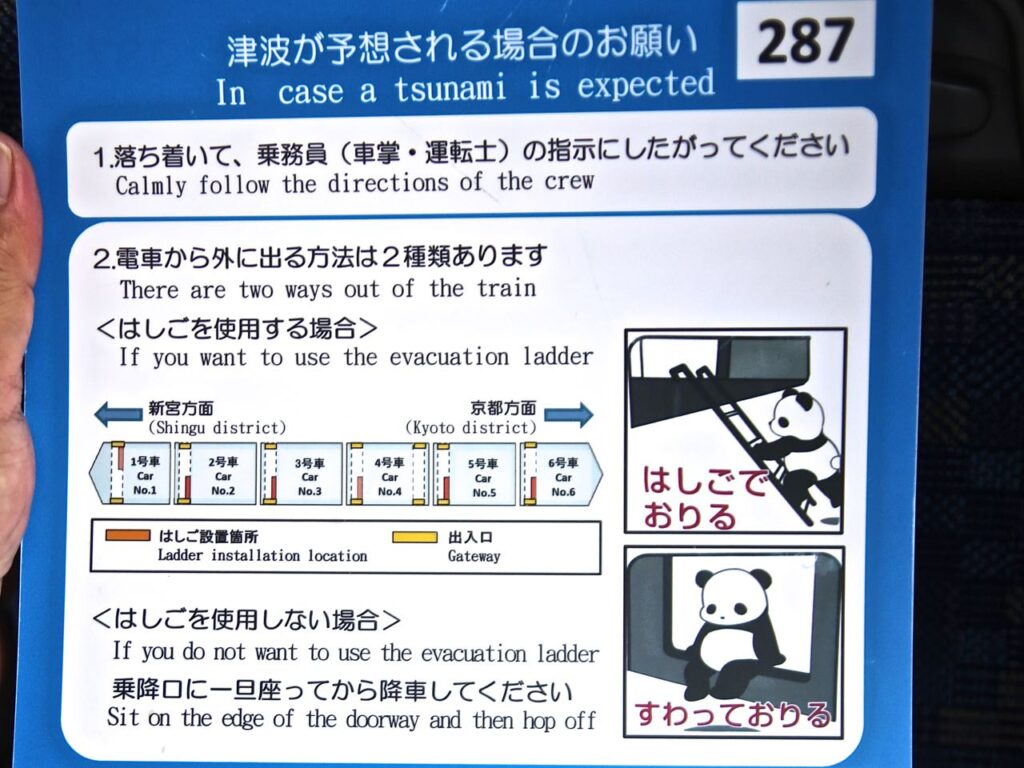
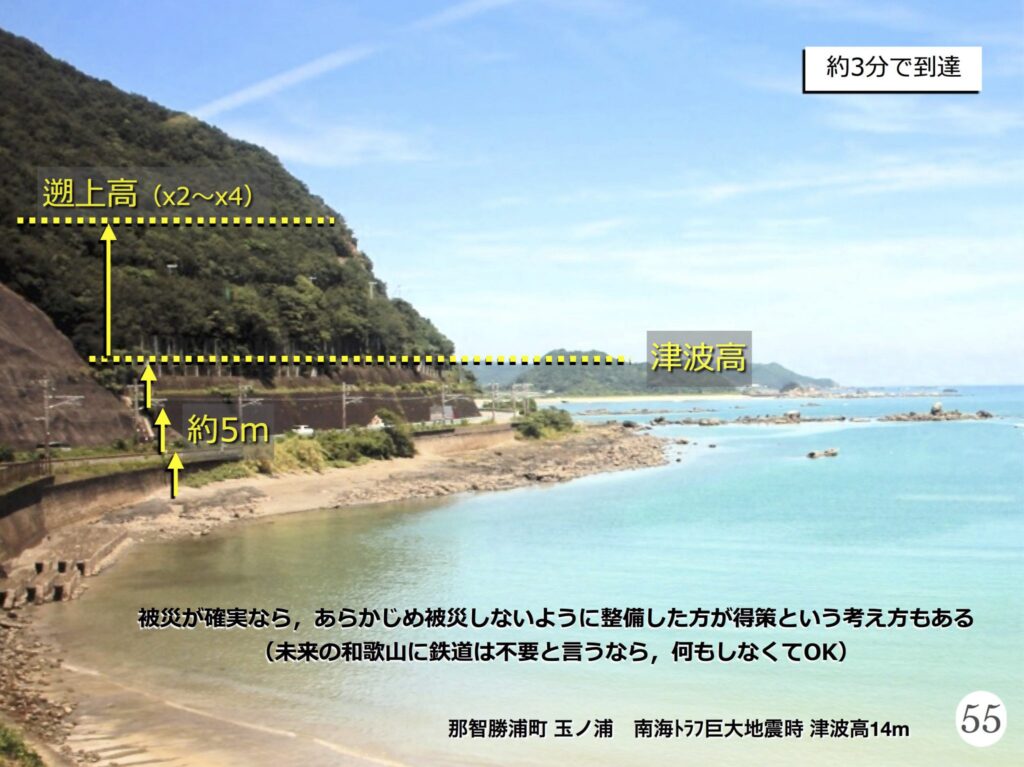





 Views Today : 315
Views Today : 315 Views Last 7 days : 3184
Views Last 7 days : 3184 Views Last 30 days : 12366
Views Last 30 days : 12366