日本では単なる連節バスを「BRT」と紹介しているようであるが,欧州では既に三連節バスが走り始めており,これを使ったBRTシステムが構築されている都市がある.
日本でも紹介が始まっているフランス東部のMetzの三連節バス.話題になりつつあるので,百聞は一見にしかず,ということで行ってみた.
通常は外側からの紹介が多いだろうが,写真整理の都合上,三連節バスの内装の紹介からである.外観の色は3-4種類あるが(緑青紫橙?),路線系統別に色分けされているわけではなく,どの色のバスが走ってくるかは決まっていない.
これは緑.前面を写しているように見えるが,実は後ろ姿である.

外観のアクセントカラーと内装のアクセントカラーは同じものが使われており,緑のバスの内装は緑系である.
下の写真は1両目後ろ側から2両目の中を写したもの.2両目は前の方にはタイヤがなくて床がフラットであり,椅子の下は空間が空いている.ここで盲導犬や介助犬が寝ていることも.
2両目の後部はタイヤの部分が出っ張っており,出っ張りの上に椅子がある.手前の円形部分は連結部分であり,ここに立っていると曲線通過時にぐるぐる回る.

3両目の一番後ろはエンジンがあったりする関係で一段高いところに5席並んでいる.手前のポールにはICカード式の乗車券のリーダーがある.
 下の写真は(紫系のバスの)1両目の後ろから運転席方向を写したものである.手前の椅子左右2席ずつはタイヤハウスの上に配置されており,かなり「標高」が高い.タイヤが丸形なので,席が背中合わせになっている.ボックス席状にするためか,さらにその前の席についても「標高」が高い(タイヤハウスがあるわけではない).
下の写真は(紫系のバスの)1両目の後ろから運転席方向を写したものである.手前の椅子左右2席ずつはタイヤハウスの上に配置されており,かなり「標高」が高い.タイヤが丸形なので,席が背中合わせになっている.ボックス席状にするためか,さらにその前の席についても「標高」が高い(タイヤハウスがあるわけではない).
左右の席間はかなり狭く,車椅子が通過できるような幅はない.通常の乗客についてもこの隙間を常々移動させるような設計ではないように見える.

丸形のタイヤハウスに席が背中合わせ…とは,こういう状態.無理矢理全席進行方向を向かせて,足の置き場に困る日本のノンステップバスよりはずっと居住性が高い.
 車椅子スペースは1両目の運転席直後のドア付近に確保されており,かなり広い.この1両目のドアから出入りすることを想定している模様.写真中央奥の席はタイヤハウスの上に設置されており,席は進行方向と逆向きである.
車椅子スペースは1両目の運転席直後のドア付近に確保されており,かなり広い.この1両目のドアから出入りすることを想定している模様.写真中央奥の席はタイヤハウスの上に設置されており,席は進行方向と逆向きである.
わかりにくいが,写っている2席の向こう側は運転席であり,運転士が運賃収受等をするような設計には全くなっていない.日本のJRの電車のように客席と運転席は完全に分かれている.

収容定員は,座席40,立ち席115,車椅子2の模様.製造メーカーはベルギーのVAN HOOLというメーカで,ExquiCity 24というタイプの模様.
動力源は通常のディーゼルエンジンの他,天然ガス仕様,トロリーバスとのハイブリッドタイプ,燃料電池,電気運転等々様々なものが準備されている模様.
残念ながら,日本の大型車メーカでは真似できないねぇ.
 やはり日本の公共交通は,車両の面でも遅れているかも.
やはり日本の公共交通は,車両の面でも遅れているかも.




















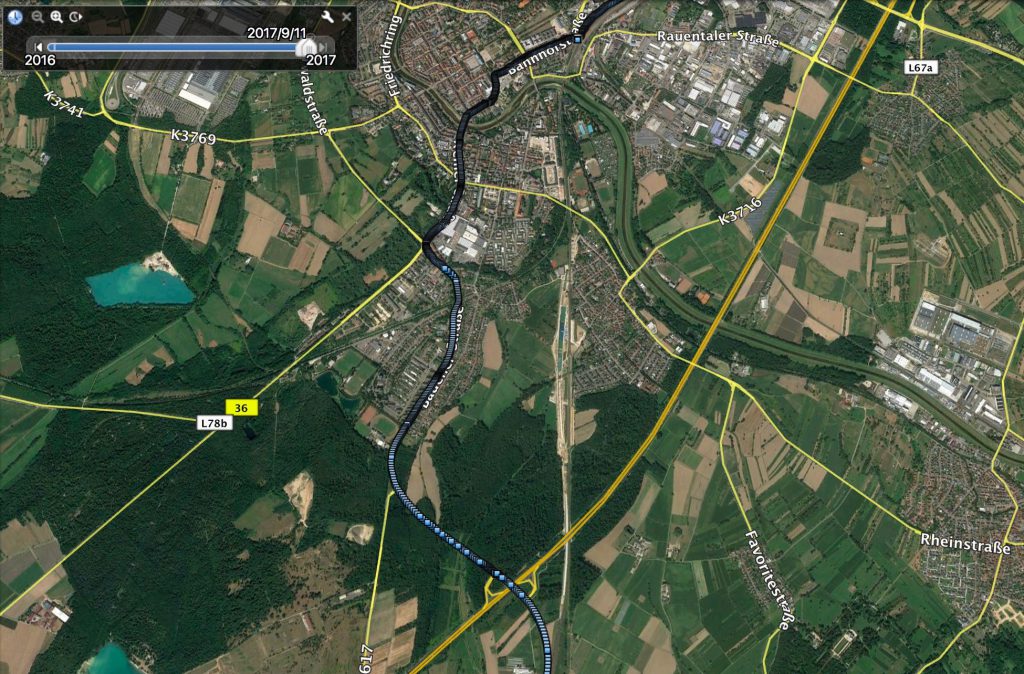







 Views Today : 309
Views Today : 309 Views Last 7 days : 2561
Views Last 7 days : 2561 Views Last 30 days : 12070
Views Last 30 days : 12070