前にも書いたがと思うが,リニア新幹線建設の大きな理由は「南海トラフ大地震こわい」である.
災害復旧能力の高い日本といえども,大津波で新幹線の線路が流されたり,100キロ,200キロ単位で震度6−7地帯を通過すれば復旧に年単位を要する可能性がある.日本の国家運営に重大な影響を及ぼす可能性が非常に大きいほか,当の鉄道会社の経営も傾きかねない.
そこで,東京-名古屋間に別線で新幹線を建設する,それが中央新幹線である.バイパスである.
さて,「中央新幹線は東海道新幹線の災害対応のバイパス」のイメージが先行している関係で,全線にわたって新線を要していると思い込んでいる人が,専門家を含めて多いのだが,よく考えてみて欲しい.
南海トラフで年単位の不通区間を生じかねないのは「東京-名古屋間」である.名古屋から西は震度5−6弱の区間が続くので,被害皆無とは言わないが,バイパス新線をつくらないといけないほどの壊滅的被害を受ける可能性は低い.
名古屋以西のルートに関して,こっちを通ると断層が1本で,こっちだと2本,などと言う専門家もいるらしいが(そもそも,地震のリスクを断層の本数で云々と言っている時点で,真剣に考えているとは言い難いが),直下の地震で数ヶ月の不通があったとしても,数兆円掛けて新線を建設しなければならないほどの理由にはならない.今まで新幹線が地震で不通になった事例は数度あるが,いずれも復旧までの期間は3ヶ月程度以下である.
そういう観点からすると,リニア新幹線名古屋以西については名古屋以東とは異なる観点で建設の是非や方法について議論する必要がある.リスクヘッジだけの観点から言うと,鉄道会社にとっては名古屋以西の建設の意義はあまりなさそうである.その実,国や沿線,与党などから早期全線完成の働きかけがあっても反応が鈍い状況にある.資金計画などを見ても,本気で取りかかればもっと早期に完成しそうにも思えるが,「様子を見てから,名古屋から西側に取りかかろうかなぁ〜」という感じである.
※資金計画の分析については,また時間があるときにでも.
※災害対応を重視するのなら,主要ターミナルが海岸の近い低地の「品川駅」の地下,水害で水没しかねない「名古屋駅」の地下,河口に近い淀川付近で津波の指摘もある「新大阪駅」って,どうよ.災害の専門家なら,誰か突っ込んでも良さそうなもんだが,誰も突っ込まないのね.名古屋市営東山線て,こないだ名駅が水没しかかってたよね.
「地震」タグアーカイブ
国道は付け替え,じゃぁ線路は?
実家附近は津波で危ないという話をしたが,その際に国道は付け替えることになっているという話もした.じゃぁ線路は?
紀伊半島の道路や線路は海岸沿いにへばりついた箇所も多く,例えば下の写真は斜面に右上から国道,南行線路,北行線路の順である.

こういう箇所であるので,津波どころか,大雨が降ると道路も線路も通行止めになることがある.津波を理由とした国道の付け替えはこの箇所もバイパスできるが,線路はそのままであり,津波危険箇所もそのままである.

「民間会社」に任せている限り,自主的に改善される可能性はほぼゼロだが,一体誰の責任でこの線路を改善するのだろうか.
ちなみに,この写真の箇所はかつての通学経路で,数千回通過したことのある場所である.
国土強靱化-幹線鉄道網でありそうな事態
リニア新幹線が整備される理由は,東海道新幹線だけに頼っていると南海トラフの地震で東西間交通が途絶すると困るから,ということになっている.資金の制約から,とりあえず2027年までに東京-名古屋間を開業,というのは今やよく知られているお話し.
一方,その先の大阪までについては,これまた資金の問題から2045年開業予定ということになっている.
ところで,「2020年,東京オリンピックばんざーい」によってすっかり影の薄くなった南海トラフ地震であるが,その発生確率は30年内に70%だとか80%だとか言われている.オリンピック開催が決まったからと言って,発生を数年待ってくれる,なんてことはあり得ない.そういえば,2011年の東北の地震が発生するまでは,次の南海・東南海地震は2035年頃,とか良くいわれてなかったっけ?
実際の発生時期は神のみぞ知る世界であるが,もっとも危惧される事態は,ほんとに2035年頃に南海トラフ大地震が起こってしまうことである.つまり,リニアが名古屋暫定開業状態で,北陸新幹線も大阪まで達していない状態である.
リニア自体はこれから建設される構造物なので,対災害については細心の注意を以て設計され建設されるが,問題なのは東海道新幹線である.補修工事が既に現時点で開始されているとは言え,静岡県下の震度7地帯,愛知県下の震度6地帯を長距離にわたって通過するので,東からリニアで名古屋まで到達できても,その先の西に行くすべがない,という事態が生じうる.
北陸新幹線も中途半端な位置で建設が止まっていたとすると,東西間移動に北陸新幹線と在来線を乗り継がなければならなくなったりで,不便この上ない.
さらに関西とってもっと悲劇なのは,この事態でリニアの西進が大幅に遅れる可能性がある.大地震が発生して東海道新幹線が途絶した場合,誰が復旧させるかというと・・・もしかしたら鉄道会社は「国の災害復旧費用で」と考えているかもしれないが,最大200兆円の被害である.国は各種の復旧工事と支援でカネが無くなるであろう.そうすると「余力があるなら新幹線の復旧は鉄道会社の自力で・・・」という話になりかねない.その東海道新幹線の復旧費用の財源はというと,元々はリニアの関西延伸に使うはずだった資金を転用ということになるだろう.
かくして,2045年リニア全線開通は大幅延期,というシナリオが発生しないでも無い.北陸新幹線を早期全通させるか,リニアを早期全通させるかしない限り,ありそうな事態だと思うのは私だけだろうか.最悪の事態は最悪のタイミングでやってくる・・・かも.
国土強靱化における幹線鉄道網最大のネック
最近の国土整備の方向性として「国土強靱化」とか「国家のリスクマネジメント」などといったキーワードが聞かれるようになってきているが,日本の幹線鉄道網については,40年前の計画から基本構想が更新されておらず,この図の路線を建設費の目処が付いた順に着工しているに過ぎない.
時々,”建設の新しいスキーム”などと称しているが,単なる資金計画である.民間が出資する場合も同じ.この図が金科玉条になってしまっている(40年前の国土整備方針なのに).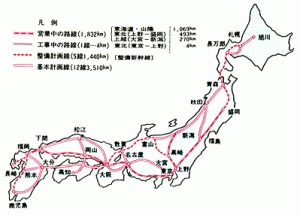
どこがネックかというと,実は「大阪」である.東海道山陽新幹線も,リニア新幹線も,北陸新幹線も山陰新幹線も四国新幹線も「大阪」が結節点になっており,ここが機能不全になると幹線鉄道網を使っての東西往来が出来なくなる.それ以外にも「東京」「名古屋」は要注意箇所であるが,それでも一応迂回ルートは存在している.
困ったことに,「大阪」は(事実上新大阪駅になるのだが)大津波時には新大阪駅は浸水被害の可能性が指摘されている.高架なら大丈夫かって? 浸水するような状況だと,鉄道を支える各種機器類や電源供給等に支障が出て,線路が無事でも機能不全に陥る可能性がある.「名駅」も津波はともかく(水害のイメージがあり)地元民は眉をひそめて大丈夫かと必ず言うし,「品川」はそもそも海岸地帯で埋め立て地である.
もちろん,この図は(いつ出来るかわからないレベルの)完成予想図であるが,在来線特急であっても事情はほとんど同じである.山陰本線は京都から分岐していると思ったあなた,あなたの頭の中の路線図は古い.京都から鳥取に向かう特急は,大阪経由の「はくと」であり,「特急あさしお」は今や昔である.
山陰新幹線を敦賀発着に,などという意見もあるかもしれないが,それがいいのかどうかはともかく,昔の「列島改造論」ベースの全体構想は,早急に見直す必要がある.
ちなみに,国土強靱化政策大綱には,「PDCA サイクルの徹底 」という項目が基本的な考え方として登場する.新幹線をはじめとする幹線鉄道もこの国土強靱化の取り扱い範疇であるが,例のごとく何もしないのかなぁ.
新聞記事の精度(京都民報編-その3)
タブロイド紙の件の続きである.コメントまだ1面だが,この面以外は独自の内容は書かれていないので,1面だけコメントすれば充分なレベルの内容である.
駅建設関係部分についても,市が噛みつかれているようだ.ポイントは,駅建設に関する費用負担である.この紙に限らず,公共事業の費用が発生することは,これ即ち全て悪であるという前提で記事が書かれることが多い.この記事も例にもれていない.
公共事業が是か非かを判断するのは,費用に見合った効果が生じるか否かであって,支出が生じることが全て悪ではない.支出ばかりで何の効果も出なければ悪い事業,支出に見合った効果が出ればいい事業.非難する場合は,何の効果も出ないということを(悪魔の証明にならない範囲で)それなりに説得力のある理由を述べてから非難する必要がある.・・・で,この記事はというと,市がまだ説明していないことだけを以て「マイナス」と結論づけている.論が飛んでますが.現時点で非難できるのは,”説明を”までですね.「マイナス」かどうかは調べたり検討したりしてないので,言えないよね.
残りの8面,9面にも記事が続くらしいが,8面は主に以下の話のダイジェスト,9面はリニア計画に反対している学者のお話のダイジェストなので,以下省略.
詰まるところ,このタブロイド紙は,茶化した記述+浅い分析+他記事のダイジェストの構成のようで,的確な独自分析には至ることが出来なかったようである.(まぁ,週刊誌なら,そんなもんか.)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(輸送力編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(失敗尻ぬぐい編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(地震対策・復興編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(環境編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(安全確保編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(番外編+まとめ)
リニア新幹線整備の理由(名古屋-大阪間:国土計画編)
リニア新幹線の東京-名古屋間については,経済効果はともかく,国土計画が40年前からずいぶん変化した現在においても,国土整備上の重要な理由が存在していることについては説明したとおりである.短期なら北陸新幹線経由で東西間を結べば数ヶ月程度なら我慢できる範囲だろう.しかし,年単位で不通の可能性があるなら,それでは具合が悪い.公式には数年単位の不通は無いことになっているが,不安な箇所が存在することは説明した通りである.
じゃぁ,名古屋-大阪間を現行計画のまま整備する理由は…?
んんんんんんんん……………………思いつかない.
確かに,中央新幹線の基本計画は奈良を経過地として指定してある.ただし,これは背景の政策が40年前の新全総であり,走行する乗り物として想定していたのは250km/h運転の団子っ鼻新幹線であった.びゅわーんびゅわーん走る,である.
残念ながら,その後の国土計画は「国土の均衡ある発展を目指した開発」の看板を下ろしてしまっている.最新の国土整備の方向性としては「国家のリスクマネジメント」であるとか「リニアを幹にして新幹線を支線に」であるとかという方針が出始めている.
そういった新しい国土整備の方向性の中で,リニア新幹線の名古屋から西はどこを走るべきか,というのは…議論されたことが…無い.「国家のリスクマネジメント」という観点だと,名古屋から西の区間についても大地震の影響を受けにくい経路を選ぶべきだという議論はあってもいいかもしれない.しかし,そうすると問題になってくるのは濃尾平野をリニア新幹線が通過することそのものだったり,果たして奈良盆地は大丈夫かとか,終点の大阪(新大阪駅?)はそもそも大丈夫かとか,そういう議論をしても良かったのだろうが,名古屋の西側については,議論はスルーで,「基本計画に書いてあるから」で終わっている.それでいいのか?
ほとんど議論に上らなかったが,首都機能の分散・移転と名古屋から西側のリニアの経路の関係はどうなんだ? これもかなり重要な議論なはずだが,基本計画に書いていることだけが理由でスルー…この国の国土計画や幹線鉄道計画は大丈夫か?
国土強靱化の基本計画が策定され,その中には計画のPDCAサイクルの実施が示されているが,日本の幹線鉄道計画はこのサイクルが欠如している.アカンやろ.
#東京オリンピックが決まるまでは,震災後と言うこともあって多少は首都機能に関する議論があった....がしかし,オリンピックが決まるとどこへやら.大災害はオリンピックがあるからといって待ってくれるわけではない.のど元過ぎるとすぐに忘れるという,日本人の悪いクセ.
津波を避けて引っ越しした話
最近,巨大津波をおそれて,静岡県などで内陸に引っ越す人が増えているらしいが,それを聞いて思いだした話がある.うちの実家がそうだった.実家は海沿いの町にある.今は海は見えない位置に引っ越したが,かつては海まで道を挟んで5-6m(5-6kmではありません)という位置にあった.海-道-家-ミカン山.外洋に面しているわけではないので,干満はあるが波はほとんどなく,普段は至って平穏.海というよりは川の河口に実態は近い.
昭和の南海地震の際に津波が家の中まで入ってきて,畳が浮き始めたので,婆さんが小学校に上がる前の父を抱いて裏山に駆け上がったらしい.その後,30年くらい経ってから孫が生まれたのを機に内陸に引っ越し.どうして周囲に親戚の少ない,学校の校区も違う場所に来たんだろうと思っていたが,最近の公表されいる浸水予想図を見て納得した.
引っ越し元はもちろん浸水実績有りだが,現実家の位置は浸水予想図では浸水高0m.どうやら,まぁ,そういうことなのかなと.なお,昔の引っ越し前の家は,今もミカンの貯蔵小屋として使用されている.

写真は実家から徒歩10分ほどの所.ここは左から順に国道-線路-市街地になっているが,数メートルの浸水が予想されており,国道については付け替えが計画されている.付け替え後の国道は現実家のほぼ真横を通るようである.線路(JR)についても,津波に関する訓練はここで行われたらしい.
東北に行ってみた(BRT編)
既にご存じの方も多いが,気仙沼線では被害が大きく,復旧の見込みが立たないことから,使用できる路盤を道路転用し,バス専用道化して「BRT」として運行されている.
拠点の停留所は「駅」として整備されており,それ以外についても屋根付きの停留所になるなど,バス路線の設備としては比較的行き届いているようだ.
下の写真は志津川.元の駅ではなく仮設商店街併設になっている.

こちらは歌津駅と一般道からバス専用道への出入り口.
[map] 歌津駅 [/map]



元々の歌津駅はこのような状態である.

いくつかのトンネルを抜けた後の専用区間北端.
[map lat=”38.736199″ lng=”141.530651″ zoom=”15″] [/map]

ここから先は橋梁等破壊されている.

 (2012年12月現在)
(2012年12月現在)
東北に行ってみた(原ノ町編)
リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(地震対策・復興編)
この意見の各項目を考えてみるシリーズの3つ目である.フルバージョンはこちら.
- 3つ目;リニア建設でなく、東海道新幹線の地震・津波対策や東日本大震災からの鉄道網の復旧を行うべきである
これには論点が3つ含まれている.
- 東海道新幹線の地震対策をすべし
- 東海道新幹線の津波対策をすべし
- 震災復旧を優先すべし
まず,地震対策であるが,これはやっている.指摘主は調査不足.やっているのにやってないというのは,さすがに鉄道会社がかわいそうである.これ以上を望むのならば,線路を揺れが襲わない地域に付け替えるか,軌道をジェットコースターのような真っ逆さまになっても脱線しない構造(レールをパイプにして,三方向からがっちり抱え込む形式)に変更するかくらいしか無い.何でも言えばよい,とうわけではない.抜き書きすると,こういうを対策実施中のようだ.
- 構造物および軌道の強化
- 高架橋の耐震補強
- 橋脚・盛土の耐震補強
- 列車を早く止める対策
- 沿線に地震計を配備
- 地震動早期検知警報システムを導入(非常停止)
- 脱線・逸脱防止対策
- 脱線防止ガード
- 逸脱防止ストッパ
- バラスト流出、盛土沈下、高架橋変位を抑制
次に津波対策であるが,これについて鉄道会社は「津波の影響はない」と言っているので,たぶん,公式には何もしていないだろう.『静岡文化芸術大の磯田道史准教授が浜名湖上を通過する東海道新幹線の津波に対する安全性に疑問を投げ掛けていることに関して「どういう根拠で言っているか分からない」と指摘』しているそうだが,公式公開資料と現地調査だけでもこういった分析ができてしまうので,やはり要注意箇所は存在する.歴史の忠告は無視すべきでない,というのは東北の震災の教訓ではなかったか?
津波対策と言っても,線路に沿って万里の長城のような防波堤を建設するわけにもいかない.危ない箇所は線路を付け替えるというのが通常の対策方法であり,例えば浜名湖を大きく迂回するか,あるいはリニア新幹線のように完全に別経路を準備するかということになる.ということなので,リニアを建設して東西間輸送を確実にするという判断は,有効な方法の一つである.
最後に東日本大震災の鉄道復旧の部分だが,そもそも鉄道会社が違うし,鉄道路線の目的も違うし,同じリソースを両者で奪い合っているわけでもない.復旧が遅いとすれば,それは(この震災に限らず),鉄道の災害復旧政策がイマイチだということであり,たたく相手を間違っている.
フルバージョンには,9兆円も金があるのなら国鉄の借金返済に充てて,それを原資に復旧すべしと書いてあるようだが,国鉄再建の枠組みを30年近くたってちゃぶ台返しする話である.事業再生の基本的な手法を知らないんだろうか.国家権力振り回して国庫に納めさせるのか?この国は独裁国家ではない.JR東海はリニア建設という形で「国家的事業」に儲けた金をつぎ込むことで,国民に利益還元しようとしていると思うが,まぁ,話が噛み合いそうにないので,この辺で.














 Views Today : 297
Views Today : 297 Views Last 7 days : 3776
Views Last 7 days : 3776 Views Last 30 days : 11649
Views Last 30 days : 11649