武豊(たけとよ)線は,東海道線の愛知県下の大府駅から分岐し,知多半島の武豊までの20km弱の路線.中部国際空港開港時にはアクセス線にしようかという話もあったが,延伸が必要だったため,お流れ.
上に「大府駅から分岐し」と書いたが,これは正確な表現では無い.実は名古屋近辺の東海道本線を建設する際,知多半島に資材を陸揚げして武豊線で運搬したので,東海道本線よりも先に建設されたという歴史のある路線である.したがって,「大府駅から分岐し」たのではなくて,武豊から北に延びる線路の途中にあった大府駅に東から来た路線が接続されたといった方が実態に近い.
さて,大府駅停車中の列車であるが,左右どちらが武豊線だろうか?

正解は,右が電車で左が汽車である.つまり,左が武豊線の列車.どう見ても両者の区別が付かない.近年沿線の住宅等の開発が進み,名古屋までの直通客が増えたので都市近郊線として電化することになった模様.
電化開業は2015年春らしいが,すでに大府駅を出ると架線が張られている.

信号機にも電車の電力用の電流と信号機用の電流を分けて通すための装置が付けられている.(でも,自動信号化はしないように見える)

全線30分あまりなので,15分毎に列車交換する.

架線は上側に電力供給を兼ねた太い線,下がパンタグラフと擦れ合う細い線.最近,首都圏や近畿圏で時折見かけるようになったタイプである.

変電所も設置されており,架線と結線されている.もうすぐ試運転始まるかな?

「車両」タグアーカイブ
CANADIAN RAIL(”2階建て”列車編)
CANADIAN RAIL(GOTRAIN編)
クルマ社会のカナダであるが,主要都市には一応,通勤鉄道がある.ただし,朝は都心方向だけ,夕方は郊外方向だけというケースがほとんどなので,興味本位で乗車すると帰ってこられない可能性があるので要注意.
例えば,オンタリオ州のトロントには「GO train」というのがある.クルマではなくて列車で「GO」というネーミングには,「via rail」と似たような切迫感がある.ただし,「GO」は「GOvernment」つまり,州政府で運営であることを表している.
車両は2階建て車両で,例の汎用機関車が端っこに付く.


もちろん,パーク&ライド対応
 機関車が端っこに1両だけで,いちいち終点では機回ししない.反対側の客車には運転席があり,いわゆる制御客車である.反対向きには推進運転になる.
機関車が端っこに1両だけで,いちいち終点では機回ししない.反対側の客車には運転席があり,いわゆる制御客車である.反対向きには推進運転になる.
プレメトロ(どう見ても”ペイ”はしないけど)
日本では地平面を走るLRTの整備ですら「採算ガー」とかいう話になりがちでさっぱり話が進まないが,海外に行くと「採算ガー」と言うような視点では絶対に「ペイ」しないような交通システムが存在していたりする.
学生によくするどんぶり勘定である.
延長5kmのLRT路線を整備したとしよう.30億円/kmの整備費用がかかったとして30×5=150億円.この線路上をLRTが走る.(実際には難しいかもしれないが)金利が3%ほどで建設費を30年で返済したとしよう.そうすると総支払額は2倍あまりの350億円ほどとして,年間の支払いは,350億円÷30年=11.6億円/年.1日あたりにすると,11.6億円÷365日=320万円.朝6時から夜11までの17時間走ったとしよう.そうすると,18.8万円/時間.片道あたりだとその半分で9.4万円/時間/片道.5分毎に走ったとして,毎時12本なので,9.4万円÷12=7800円/列車.1人あたり200円払ったとして7800円÷200円/人=39人.朝から晩まで5分毎にやってくる電車は全て約40人乗っている・・・・全て運賃で賄うって厳しいねぇ.まだ電気代も,人件費も払ってないよぉ.
さて,ベルギーのアントワープ駅の地下にはLRTの発着場があり,地下鉄風だが走ってくるのはLRT用の小さな電車である.プレメトロという.

和蘭のアムステルダムでも地下鉄かと思いきや,LRT風電車が2編成併結でやってきたりする.

こういった地下線は,地平に線路を敷くよりも建設費がかなり高く,キロあたり100〜200億円くらいはする.そうすると,上に書いた計算式の数字はそれぞれ5倍くらいになり,おおよそLRT用の電車では運びきれない数字になってしまう.
つまり,こういう地下を走るLRTというのは,日本の「採算ガー」とかいう風土では絶対にあり得ない交通機関なのである.でも,ベルギーやオランダには存在するし,クルマ社会の米国サンフランシスコにもあったと思う.交通機関単体では「採算ガー」採れませんが,都市全体としてはこうした方が適切であるとの判断で導入されている交通機関であるとも言える.
日本の「採算ガー」・・・何とかなりませんかね.それにこだわって失ってるものがいろいろありそうです.
車両と構造物の”限界設計”
構造物の限界状態設計法のお話し,ではありません.
英国ロンドンの地下鉄は,ご存じの人も多いように変な形をしている.ここまで切り詰めれば,無駄なしという感じの形状で,まずトンネルあり,それに合わせて電車ありという断面である.特に屋根の形状が特徴的で,出入り口の上方は丸く湾曲している.
おそらく初期の路線で建設費を抑えること,電車がここまで大量輸送に使われることを想定していなかったことなどから,小型車両が使われ,その後,電車の大型化に伴ってトンネルぎりぎりまで大きくなったのではないかと思うが,何かあった場合には逃げ道は前後方向以外存在しないなとも思う物理形状である.

日本では近年,工事費を抑えた地下鉄としてミニ地下鉄が建設される場合があるが,トンネル断面積ではこのロンドン地下鉄の方が小さい.ということは,日本でもここまで割り切ることが出来れば,さらに地下鉄の建設コストを下げることが出来る可能性はあるが,「安全性がー」と言う話になって,実現しないだろうなぁ.ロンドンで実用になっているのだから,日本でも問題ないと思うのだが.
レールだらけ(地下鉄編)
鉄道線路は左右のレールが1組になっている。わざわざ言わなくても、子供でも知っているお話。ちょっと詳しい子供なら、地下鉄には3本目のレールがあることを知っていることもある。
第三軌条(サードレール)と言って、地下鉄電車に電力を供給するためのレールで、その代わりに屋根上の架線が無い。架線が無いとその分だけトンネルを小さくできるので、建設費を安く抑えることができる。
じゃぁ、この地下鉄は? レールが4本ある。ロンドンの地下鉄。最も左のレールは電力供給用、左から2番目と最右端のレールは車輪が走行するためのレール。じゃぁ、中央のレールは?

中央のレールも電力供給用。最も左のレールと中央のレールには碍子がついており、絶縁に気が使われていることがわかる。この2組でプラス極とマイナス極(厳密にはちょっと違うようだが)になっている。通常は走行用のレールをマイナス極と共用にするのだが、ここでは別にレールがわざわざ準備されている。
別にすることのメリットとしては、変電所に帰る電流が地中などを伝って思いもよらない箇所に電蝕…つまり一種の電気分解ですね…の影響を与えることを防いだり,電車のボディーとホームとの間に電位差が生じて乗客が感電したりすることを防げる(だったっけな)。
これは日本的基準ではBRT?
日本的基準では連節バスはBRTのようだが,じゃぁ,後ろに延ばすのではなく上に積み上げても日本的基準ならBRTになりそうなものである.
さらに,その中量輸送相当のバスがウジャウジャ専用レーンを走っていたら,これは「大量型軌道」か? こうやって極端な例を考えてみると,何がおかしいかがわかりやすい.LRTやBRTは確かに「中量輸送」ではあるが,輸送量の多寡だけが都市交通の仕分けの基準ではない.都市内においてどんな役割を担うのかを考えて基準を設けないと,変な話になってゆく.
こうやって極端な例を考えてみると,何がおかしいかがわかりやすい.LRTやBRTは確かに「中量輸送」ではあるが,輸送量の多寡だけが都市交通の仕分けの基準ではない.都市内においてどんな役割を担うのかを考えて基準を設けないと,変な話になってゆく.
似たような話は,「街路の規格」にもある.日本の基準では街路は自動車交通をどれだけの量,どれだけの速度で通すかしか基準がない.そろそろ,いろいろ見直した方が良さそうだ.
茨城県のBRT(ひたちBRT編)
日立にもBRTがあるようなので,立ち寄ってみた.日立駅ではなく,大甕(おおみか)駅発着.ここも日立電鉄線の廃止線路跡をバス専用道として活用している.廃止路線の代替バスというわけではないようである.



大甕駅から少し南下した地点から線路跡地転用の専用道路に入る.ここは一般道からの出入り口で,やはりバス側に遮断機がある.


このバスのおもしろい点は,整理券がICカード化されていることである.現金精算時の取りっぱぐれ防止策としては,世界一かもしれない(が,それでいいのか?).運営事業者が日立製作所グループだから,機器類のショーケースと理解すればいいのだろうか.

専用道路はさほど延長は長くないが,全線にわたって歩道が整備されているのでこの専用道にぶち当たりさえすれば,停留所にたどり着くのは容易である.地元住民のお散歩コースにもなっているようである.

停留所部分で行き違いが出来るようになっているほか,要所要所でも交換できるように道路が部分的に太くなっている.停留所は屋根付きだが,かなりシンプル.


歩行者用の「踏切」もある.

一般道との交差点については,バス道路側に遮断機があるのは「かしてつBRT」と同じ.信号機付きの場所もあれば,単に一旦停止の場所もある.

元日立電鉄の久慈浜駅で専用道は終了.ここから先は一般道を走る普通のバスである.

CANADIAN RAIL(へろへろ線路編)
大陸の鉄道はおおらかである.こういう線路でも現役で使われていたりする.といっても,写真は10年以上前のものだが,Googleで確認してみると,今もあまり変わらないようである.
場所はこのへん.
日本に本物のBRTは出来るか?(ガイドウェイバス)
名古屋のバスは昔から結構がんばっている(お土地柄,戦果は厳しいが).
大曽根駅から北東に延びるゆとりーとラインはガイドウェイバスで高架上を走るバスである.一応案内軌条の軌道扱い(要するに電車の仲間)であるが,バス専用道を走るバスであることに間違いない.
高架なので,乗り降りが少々面倒であるが,走ってしまえば信号待ちはないので,スムーズではある.

しかし,見てのとおり,高架構造物を作らなければならないので建設費が高く,「ペイするか」という視点が導入された途端に急速に意気消沈してしまうようなシステムであり,ここ以外には話は続かない.軌道法適用条項を外せば部分的な導入は効果があると思うが,残念ながらお役人様の頭はさほど柔軟ではない.ガイドウェイバス自体はBus Rapid Transitの要素をかなり満たしており,あとは使い勝手の面を拡充すれば十分にBus Rapid Transitである.日本の自称BRTは「安かろう」が前面に出すぎて,何を満たせば便利に使ってもらえるのかの検討が不十分だと思うのは気のせいか?BRTの基準て何だったっけ?



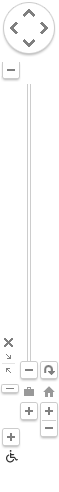





 Views Today : 16
Views Today : 16 Views Last 7 days : 2257
Views Last 7 days : 2257 Views Last 30 days : 14248
Views Last 30 days : 14248