まぁ,わかってたんですけどね.
半室グリーン車のなので,どの席選んでもほぼ台車の上.
おまけに振り子式電車なので,揺れる揺れる揺れる.
まぁ,わかってたんですけどね.
ちょっと指定席おさえるのが遅かったんで,グリーン車しか無かったもんで.
他のJRの特急に比べてグリーン料金が安いんで,何とか許せるギリギリだが,揺れる揺れる揺れる.
小倉まであと1時間.
うぅぅぅ〜
#新幹線て,やっぱり楽だわ.

まぁ,わかってたんですけどね.
半室グリーン車のなので,どの席選んでもほぼ台車の上.
おまけに振り子式電車なので,揺れる揺れる揺れる.
まぁ,わかってたんですけどね.
ちょっと指定席おさえるのが遅かったんで,グリーン車しか無かったもんで.
他のJRの特急に比べてグリーン料金が安いんで,何とか許せるギリギリだが,揺れる揺れる揺れる.
小倉まであと1時間.
うぅぅぅ〜
#新幹線て,やっぱり楽だわ.
水道事業の民営化を進めるという話があるらしい.
上水道設備のインフラが老朽化してきているので,それの設備更新が民営化によって効率的に進むことを期待しているらしい.人口減少対策らしい.
…が,しかし.海外に目を向けなくても,既に民営化したインフラの更新が進んでいるかどうかは鉄道を見ればよくわかる.
ごく一部の儲かる地区では設備投資される一方で,そうじゃ無いところでは放置されているのが現状だ.儲かる地区でも,設備投資されるのは商業設備などの儲け直結部分だけで,地味な輸送の基礎インフラは放置されていることは少なくない.
新規の鉄道線はというと,新幹線にしろ都市鉄道にしろ幹線鉄道にしろ,鉄道事業者単独事業はかなり希であり,国や地方などの行政が金を出さない限り前には進まないし,改良事業もしかり.地方ローカル線は放置状態で自然災害で破壊されるのを待っている状態ではないかと思うことも少なくない.
水道事業民営化によって,人口減少下においてインフラ更新が進むってのは,少々お花畑ではないかな.あるいは国民をだまして,特に人口の少ない地域での棄民政策か? 水飲めなきゃ,すぐ死ぬぞ.
#1 民営化していい方向に進むには,少なくとも多少なりとも競争状態が必要では?
#2 JR北海道で信号機が倒れたね.「地味な輸送の基礎インフラ」の一つ.
名鉄駅の難易度が高いだけでなく,め〜駅(名古屋駅のことです)は全般的に難易度が高い.
新幹線に乗って通過するだけの人が多いせいか,名古屋駅は東西が長手方向だと思っている人が多いが,東京からやってきた新幹線は南側から回り込んで北に抜け,その後徐々に西に向きを変える.
なので,ナゴヤン以外の人が思っている方向とは向きが90度違っている.まず,これがわかりにくい原因の一つ.
次に駅舎からの出口だが,主なものは「桜通口」「広小路口」「太閤通口」…
ナゴヤンは桜通が東西方向のメインストリートの一つで都心方向に向かうならこっちだと知っているが,非ナゴヤンにとっては,せいぜい地下鉄にそんな名前の路線があったっけという程度.
ややこしいのが「広小路口」と「太閤通口」.特に「太閤通口」がクセもので,連想ゲーム的には「太閤→秀吉→昔の人→もしかしてお城?→都心方向」と感じてしまう.
実際には「太閤通口」は他都市なら「新幹線口」とか名乗っていそうな方向であり,都心方向とは逆である.(名駅の新幹線口は駅コンコースから新幹線に直接ホームに入れる改札のことであり,南北2カ所ある)
「広小路口」もメインストリートに出るのかと思いきや,主な使い道は名鉄や近鉄との乗換である.駅の正面ド真ん前に出たければ「桜通口」.
なお,名古屋城は秀吉築城では無くて徳川によるものであり,太閤とは太閤殿下が”新幹線口”側の中村区生まれだからである.
じゃぁ,簡単に「東口」「西口」「南口」「北口」にすれば解決するかというと,冒頭に書いた「90度問題」が顔を出す.そしてまたリニアが出来ると,またまた駅の構造が複雑になって,難易度が上がるんだろうか.
名古屋を訪れる機会が増えて四半世紀.いまだにわかんねぇ〜よ.
(すぐにリンク先が消えそうだが…)
健康への影響が指摘される極めて小さい粒子状の大気汚染物質、PM2.5について、慶應大学のグループが地下鉄で調査をしたところ、最大で地上のおよそ5倍の濃度にのぼったことがわかりました。
情報源: 地下鉄で高い濃度のPM 2.5|NHK 首都圏のニュース
原因はレールと車輪の間の鉄粉みたいだが,鉄粉が出るのは両者の間の摩擦力が原因なので,防止するには地上側と車両側との間のブレーキ力をレールに伝えなければ解決できるということかな.
ということで,解決方法はこれかも.
リアクションプレートに力を伝えて加速,減速をするので,車輪は原則として車重を支えるだけ.
難点は,たぶんモータを発電機として走行エネルギーを電気エネルギーとして回収しにくいことかな.(一応回生ブレーキはある模様)
#レールと車輪の間の鉄粉よりも,タイヤとアスファルトの間で生じる粉塵の方がヤバいと思う.
#今日は新橋-横浜間開業から146年目.今年は明治150年らしいので,明治政府は4年で鉄道開業させたわけやね.
スペインの鉄道博物館,他の展示物はこれといって面白いモノは無い(…と言ってしまうと失礼だが,正直な感想である).
そんな中,スペインらしい展示物がこれだ.
 登場して75周年らしい.期間限定特別展示.といってもパネルだけ.
登場して75周年らしい.期間限定特別展示.といってもパネルだけ.
 スペインのタルゴというと,人によって受け止めるイメージは異なり…
スペインのタルゴというと,人によって受け止めるイメージは異なり…
…と様々であり,どれが真の姿かというと,どれも正しい.つまり,振り子式列車バージョンも,フリーゲージ列車バージョンも,300km/h超運転できる高速仕様もある.
 スペイン国外にも輸出されており,各国仕様があるようだ.ゲージが異なる路線を直通という点では欧州にはロシアという広軌鉄道網を持つ国もあり…
スペイン国外にも輸出されており,各国仕様があるようだ.ゲージが異なる路線を直通という点では欧州にはロシアという広軌鉄道網を持つ国もあり…
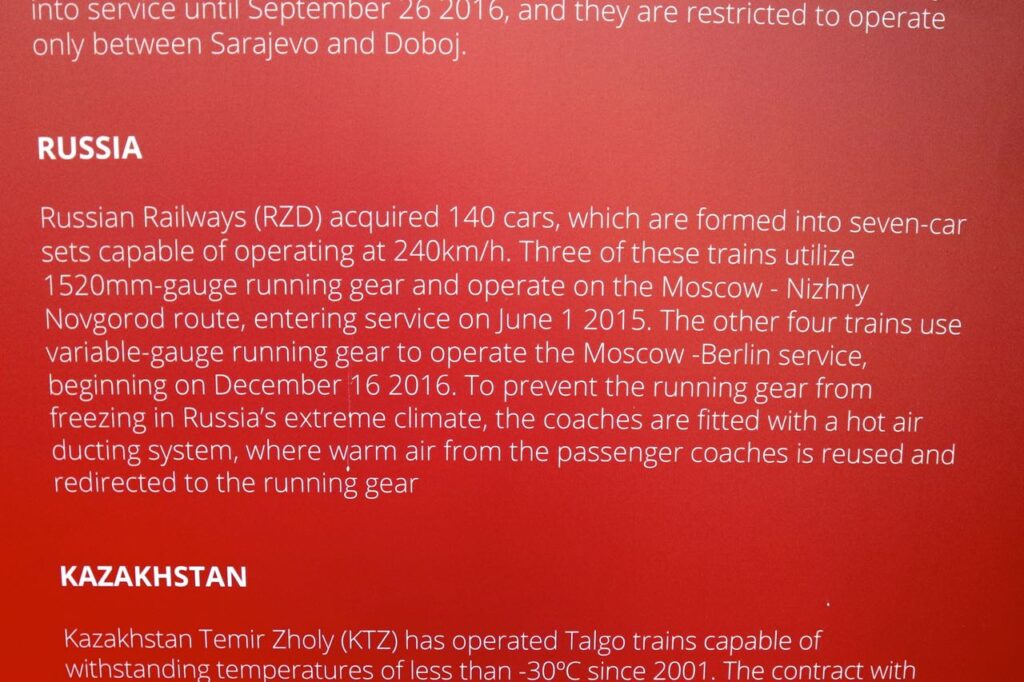 ロシア鉄道では240km/h運転できる上,7編成のうち3編成は1520mmの広軌区間で使用され,残りの4編成は2016年からモスクワーベルリン間に投入されて軌間変換装置を使っているようだ.
ロシア鉄道では240km/h運転できる上,7編成のうち3編成は1520mmの広軌区間で使用され,残りの4編成は2016年からモスクワーベルリン間に投入されて軌間変換装置を使っているようだ.
JR東日本が検討している秋田新幹線の岩手、秋田県境の新ルート整備で、同社が600億円規模の概算事業費を秋田県や沿線自治体に対し提示していたことが7日、分かった。トンネル新設を含む工事区間は県境をまたぐ十数キロになるとみられる。
情報源: <秋田新幹線>新ルート整備600億円試算 トンネルは10キロ超、工期10年見込み | 河北新報オンラインニュース
関連記事もある.
情報源: <ニュース深掘り>秋田新幹線新ルート整備 防災強化へ議論不可欠 | 河北新報オンラインニュース
山形新幹線の福島-米沢間と似たような事情だが,山形新幹線が「新幹線計画路線に並行する在来幹線鉄道」であるのに対し,こちらは事実上都市間の幹線として機能しているものの地方交通線であり,こちらは公式の新幹線計画は無い.
両記事をよく見ると,どちらにもフル規格新幹線電車を通過させるには追加費用が○○○億円という件も無い.
秋田市への新幹線計画は日本海側の羽越新幹線計画,福島から山形を経由して内陸を縦走する奥羽新幹線計画がある.ところが秋田への現状の主たる幹線鉄道輸送はどちらでも無く,盛岡からの田沢湖線ルートだ.
整備費用は山形新幹線に比べると小さいモノの,状況的にいろいろと悩ましい.簡便な整備は現状のルートを強化することだが,公式の新幹線計画が無いのでフル規格新幹線電車を通過させるトンネルを建設するのが難しそうである.このプロジェクトは在来幹線鉄道の改良工事になってしまい,新幹線整備ではないので国の補助制度メニューもしょぼく,補助率も新幹線建設に比べて小さい.
これに加えて,現状のルートをフル規格新幹線化させた場合,奥羽新幹線や羽越新幹線沿線地域はどうするんだという問題もある.
もっとも,奥羽新幹線がもし完成したとしても,現状の田沢湖線ルートは隣県の県都である盛岡とを結ぶルートであることに変わりは無いわけで,少なくとも防災目的の投資は無駄にはならない.
新トンネルは時間短縮にもつながるそうだが,10キロほどのトンネルだと,急加速しても250キロに達するのは難しそう.時間短縮の恩恵も小さく,170キロ運転程度を念頭に設計しておくというのが無難な落としどころか.170キロなら久留米と新鳥栖のわずか数キロでも到達できる速度だ.いずれフルサイズの電車は山形方向からやってくると期待すれば,トンネル径は在来線サイズでもいいかなぁ.
山形新幹線の山形、福島両県境区間で豪雪などによる運休や遅延が相次いでいることを受け、JR東日本は、防災対策事業の概要をまとめた。
情報源: 運休相次ぐ山形新幹線…トンネル新設の工事費は1500億円 JR東、事業化の是非を検討 – 産経ニュース
例の「山形新幹線最弱伝説」への対応である.いっぺん言及した件でもある.
この記事をよく見ると,120億円追加すればフル規格の電車が通過できるトンネルサイズにできる,とある.ということは,原案は在来線サイズのトンネルということか.
この区間(福島ー米沢間)は新幹線の基本計画である奥羽新幹線の一部でもあるので,「常識的には」フル規格対応で作っておいて,必要に応じて転用するのが妥当だろう.いったん完成して使い始めると出戻り工事は不可能だからだ.まぁ,要するに青函トンネル方式である.
正式な高速道路が欲しいんだが,なかなか整備されない区間において,まずは一般国道のバイパス的な自動車専用道路を建設(線形そのものは高速道路で対面通行など)しておいて,時期が来たら高速道路網に組み込むということが行われることがある.「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路」というやつである.
例えば,和歌山の海南湯浅道路(国道42号)→阪和自動車道,とか,高松東道路(国道11号)→高松自動車道とか.そのほか,高速道路への正式編入はされていないものの実質的に高速道路網の一部になっている自動車専用道路は全国にたくさんある.
高速道路以外にも,一般国道2号のバイパスを有料の県道として整備した欽明路道路(30年くらい前に無料開放)というのもある.
そういったアイデアが新幹線ネットワークにあってもいいと思うんだが,「常識」の通じない頭の固いセクションがあると実現しにくいかも.
山形新幹線については最近もさらに別のトンネルの建設を要望する記事があったが,米沢盆地と山形盆地の間の山地部分あたりかな?