二項目目にいってみよう.話題の対象はこれである.今回は,「2. 大阪の経済成長戦略」のうちの産業振興関係の部分である.
大阪は世界に通じる都市としてのポテンシャルを有しています。
ま,そうだね.
しかしながら、府と市の縄張り争いにより、そのポテンシャルを十分に発揮できない状況が長らく続いてきました。府市一体となった成長戦略を展開し、多様な相乗効果を生み出すことで大阪の成長を強力に進めていきます。
そのロジックだと,ソースタコヤキがミソシャチホコに負けた理由がわからんがね.仮説(=大阪市が政令指定都市だから大阪は発展しない)を設定し直した方がいいのでは?
各論を見てみよう.
(1)産業育成のための基盤整備
・府大と市大の統合
・府立産業技術総合研究所と市立工業研究所の統合
・産業振興機構の府市統合・機能強化
産業育成のための基盤整備が,なぜか全て「統合」になってしまっている.統合して相乗効果が見込める場合には1つにまとめることは有効だが,単なるコストカットだと何も起きないよね.大阪における産業基盤育成のポイントは,主要拠点の「統合」じゃなくて,以下の各点じゃないかな.
- 既存の産業集積の利用(=全体規模が大きい)
- (京阪神を含めて)高度な研究活動拠点の活用(=質を高められる)
- 多数の中小企業の活用(=多様性が確保できる)
これらを生かすことができて,初めて大阪らしい産業基盤整備が可能になる.そうすると,「府大と市大の統合」ではなくて「府大や市大などの研究拠点と既存産業集積とを密接につなげる」ことや,「公立の研究所の統合」ではなくて「公立の研究所と既存産業集積とを密接につなげる」ことが大阪復活のキーポイントになるんじゃないだろうか.そして,単に規模の大きいことだけが強みではなくて,リンク先は多種多様な企業にすることも可能なわけだ.そのためには産業振興機能の強化が必要になる,産業のダマゴやタネになる話を研究拠点の中から見いだす目利き機能が必要になるんじゃないのかな.(まあ,つまり,上の(1)の各論は早速,主要なポイントを外しているんじゃないか,ということ)
(3)先端技術産業の拠点形成
・創薬の促進
・医工・看工連携による先端医療機器・サービスの開発
・新エネルギー(水素、蓄電池等)開発支援
あら…? 大阪にはもっと多くの先端産業がありませんでしたっけ? ロボット産業とかも,ありませんでしたっけ? バイオ関係は強いですが,薬だけがバイオでもないような.それから,肝心の研究拠点が逃げ出すような地域環境なんですけど,どうしましょうか.武田薬品の研究所が首都圏へ行ってしまって大騒ぎになったのは記憶に新しいところ.神戸には世界的にも最速級のスーパーコンピュータがあるので,それを活用した産業もいいですね.さらに西にはSpring8なんてのもありますが.大阪じゃないから活用しないの? 大阪は(本来は)西日本の盟主(のはず)なので,そういった広域的なリソースの活用を考えてもいいんだけど,発想がなんだか狭い範囲しか考えてないよね.
(5)中小零細企業の応援
・保証協会の強化
・商工会議所・府の経営相談窓口強化
・海外展開の支援
まぁ,そういう機能も必要なんだが,中小零細企業の泣き所は研究開発に資金拠出しにくい経営環境というのも大事なポイントであり,上の(1)関係のコメント参照.
数年前からずっーーーと感じているんだが,あんまり良い政策ブレーンがバックにいないよね.
つづく
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
あーこわいこわい.





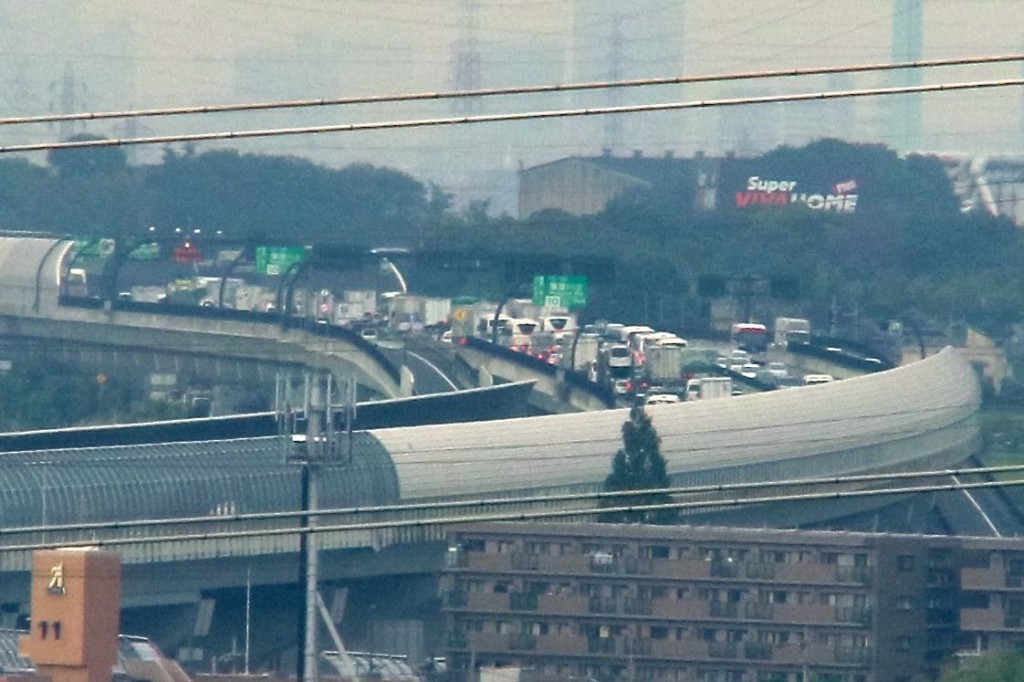







 Views Today : 178
Views Today : 178 Views Last 7 days : 2760
Views Last 7 days : 2760 Views Last 30 days : 12073
Views Last 30 days : 12073