北陸新幹線の敦賀-大阪間の建設費が高めになっている原因を考えてみようということで,前回は敦賀-新大阪間を大深度地下じゃなくて「普通に建設したらいくら掛かるか」を計算してみた.
今回は京都と大阪の地下線区間をどの程度に見積もっているかを探る話である.
方法としては,都市部の地下線区間とそれ以外について,まずは「普通につくったら」いくら掛かるかを計算してみる.
まずは,地下線以外の区間部分.
| 費目 | 単価 | 単位 | 単位数量 | 数量 | 小計(億円) | 備考 |
| 用地費 | 5.24 | 億円/km | 軌道延長 | 191.9 | 1,005.5 | |
| 路盤費(複線) | 55.10 | 億円/km | 区間長 | 0 | 0.0 | |
| 橋梁費(複線) | 41.37 | 億円/km | 区間長 | 21.44 | 886.9 | |
| 隧道費(複線) | 32.22 | 億円/km | 区間長 | 74.5 | 2,400.5 | |
| 軌道費 | 1.86 | 億円/km | 軌道延長 | 191.9 | 356.1 | |
| 停車場費 | 122.8 | 億円/箇所 | 施設数 | 1 | 122.8 | |
| 車庫・検査修繕施設費 | 782.4 | 億円/箇所 | 施設数 | 1 | 782.4 | 久御山基地 |
| 諸建物費 | 0.11 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 10.4 | |
| 電灯・電力線費 | 0.95 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 90.6 | |
| 通信線路費 | 1.03 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 98.1 | |
| 運転保安設備費 | 1.57 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 149.6 | |
| 防護施設費 | 0.39 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 37.4 | |
| 電車線路費 | 0.40 | 億円/km | 軌道延長 | 191.9 | 77.3 | |
| 変電所費 | 2.24 | 億円/km | 工事延長 | 95.29 | 213.5 | |
| 工事関係 | 15.1 | % | 対上記合計 | 940.9 |
地下線以外の延長は95.3kmで単純合計7,172億円(2010年価格)になる.
建設費を「建設工事デフレータ」で調整してみると…
7,172億円×(122.5/93.4)=9,407億円 (2023年)
さらに,金沢-敦賀間が+28.8%の上振れをしていたことを織り込むと…
9,407億円×1.288=1兆2,116億円
ちなみに,キロあたり単価はこうなる.
1兆2,116億円÷95.3km=127.1億円/km (2023年)
ところで,前回の「敦賀-新大阪間を普通につくってみる」見積もりは1兆7,487億円だったので,京都や大阪の地下線区間部分を「普通につくってみる」場合の見積もりは,延長48.7kmに対して差し引き5,371億円ということになる.
1兆7,487億円-1兆2,116億円=5,371億円 (地下線区間を普通に計算した場合)
さて,公式見積もりの3.9兆円には地下線以外の区間も含まれているので,3.9兆円から地下線以外の区間の費用(上記の1兆2,116億円)を差っ引くと,地下線部分の見積もりということになる.
3兆9,000億円-1兆2,116億円=2兆6,885億円 (地下線部分の見積もり)
要するに,地下線部分は通常の見積もりに比べて,以下の倍率で計算していることになる.
2兆6,885億円÷5,371億円=5.01倍 (地下線部分の通常区間比)
ご5倍!
キロあたり単価はこう見積もっているようである.
2兆6,885億円÷48.7km=551.9億円/km (地下線部分のみ)
うーん,確かに地下線工事は高額かもしれないが,市街地ばかりを通る通勤通学用の地下鉄の工事費がキロあたり250-400億円なのに,駅が少なくて(*)郊外部分も多い新幹線がいくらなんでもキロあたり550億円overってちょっと見積もり高すぎでは?
(*)地下鉄工事は駅が高い.

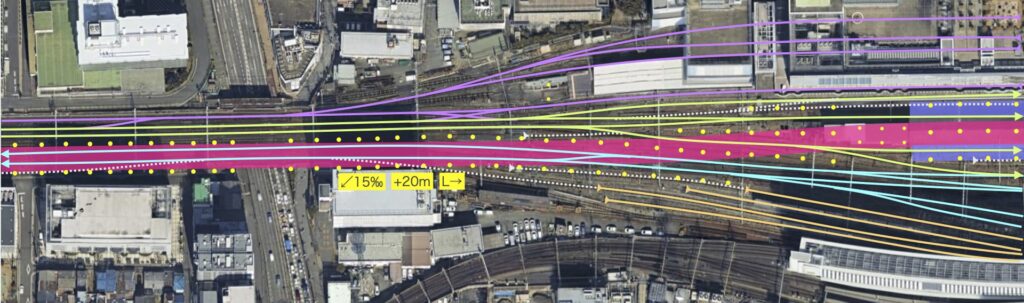
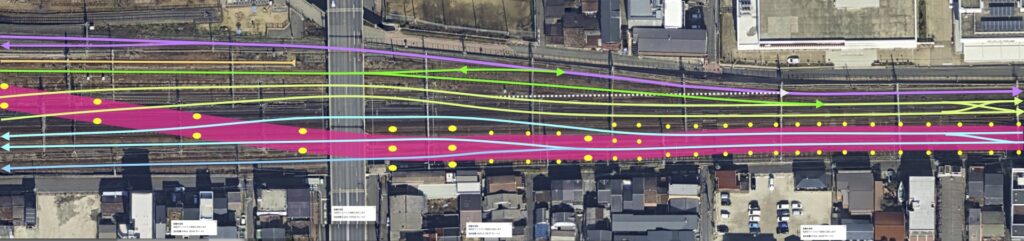

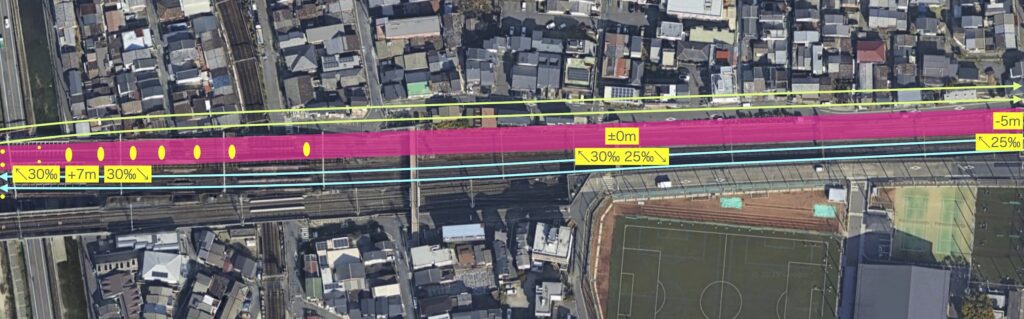

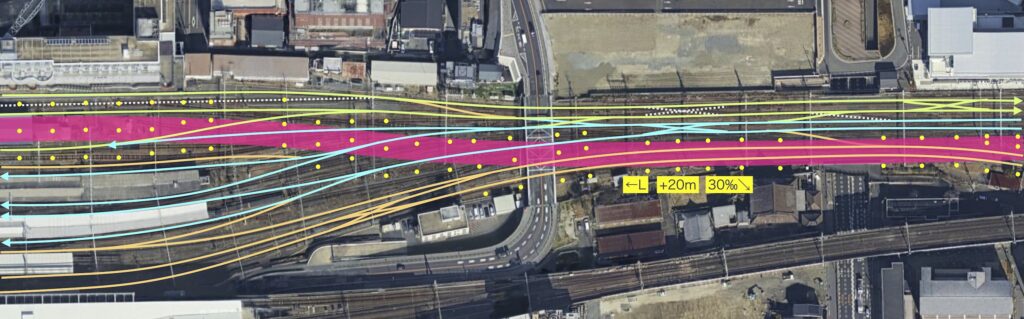

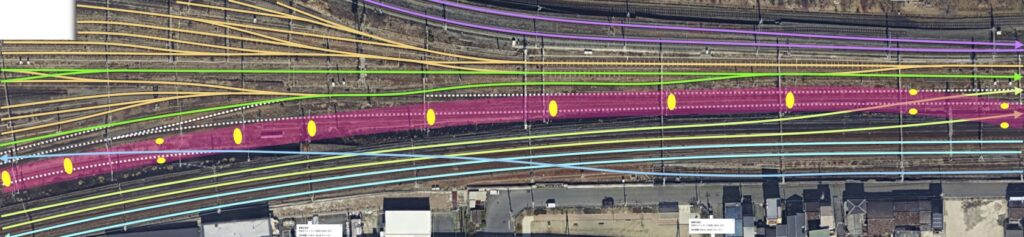
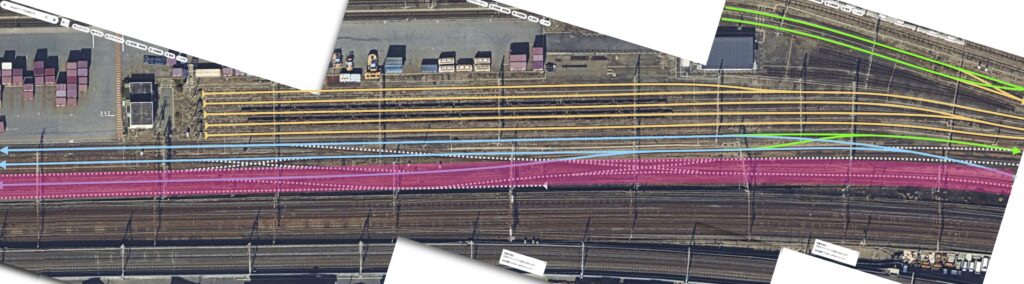
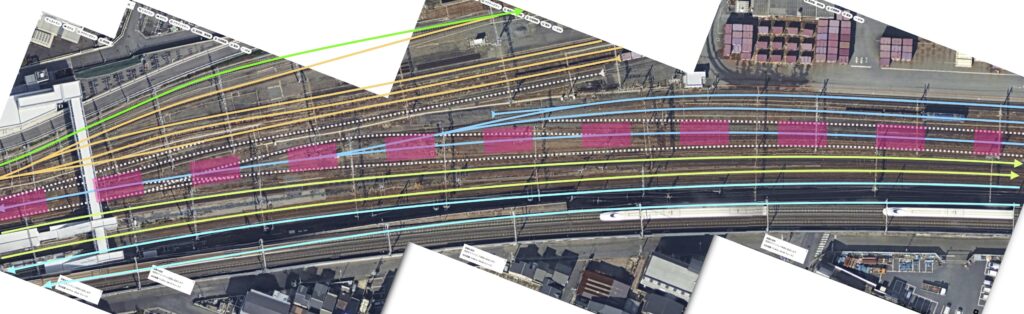
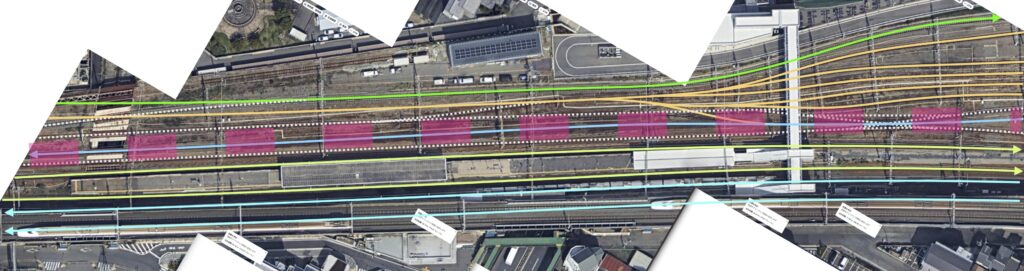
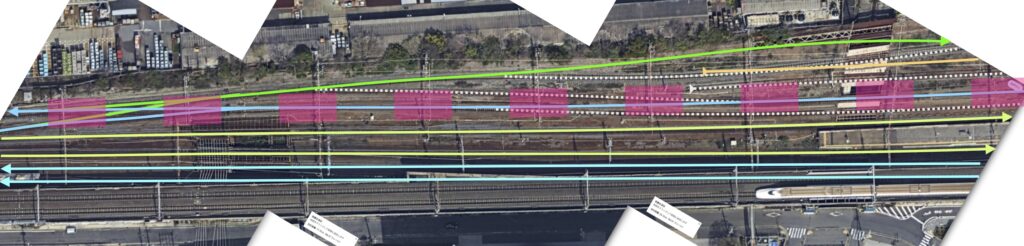

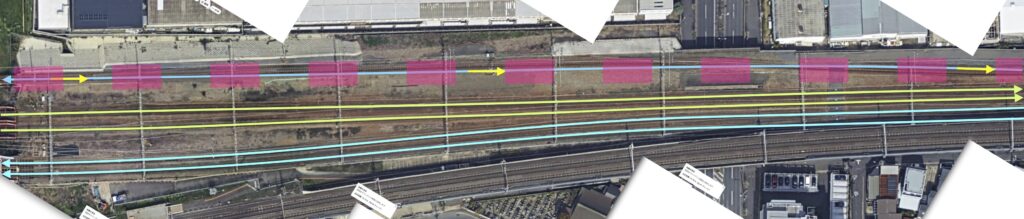

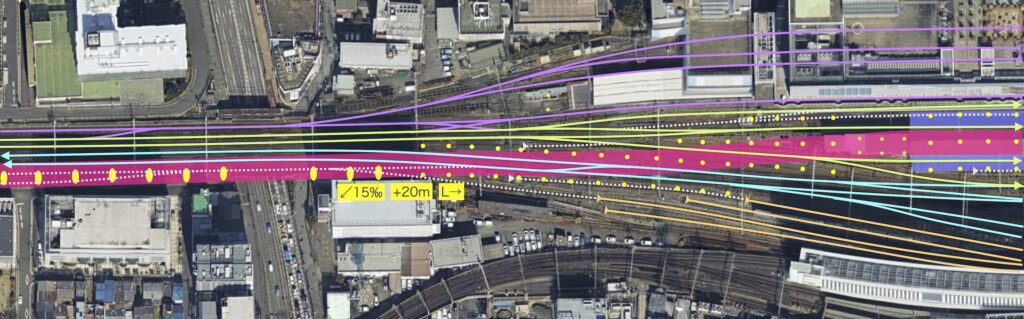

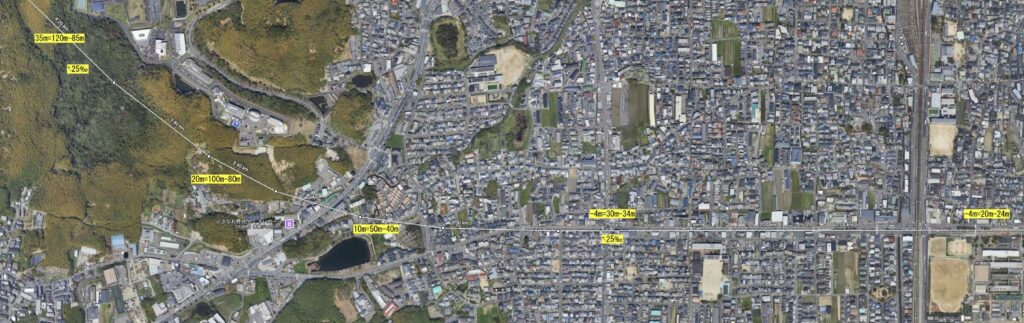
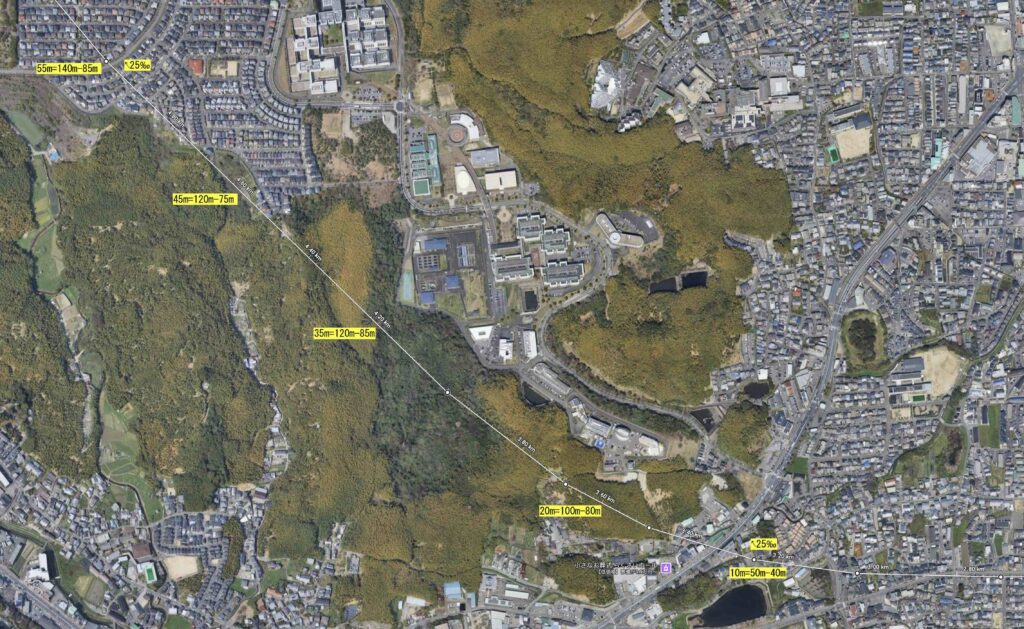
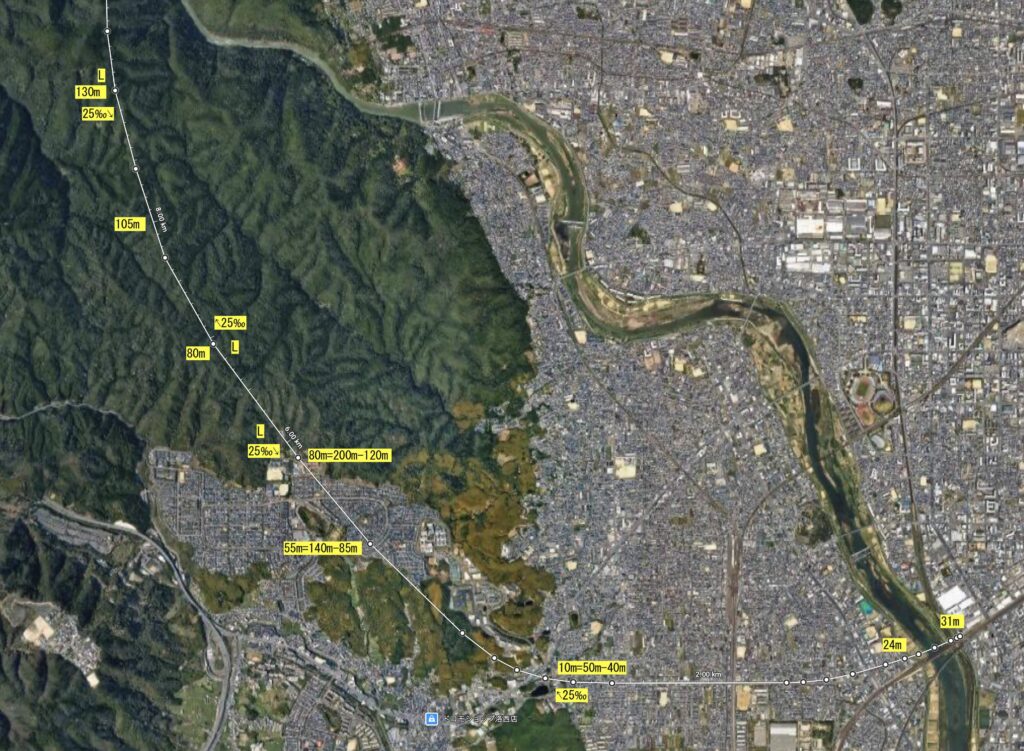






 Views Today : 390
Views Today : 390 Views Last 7 days : 3227
Views Last 7 days : 3227 Views Last 30 days : 12891
Views Last 30 days : 12891