第三夜なので,もはや初夢というべきかどうかはともかく,こんな夢を見た.
2014年度終わり頃になって北海道新幹線の開業前倒しが決まり,その当時は2030年頃に開業することになった.その当時は,と書いたのは実はさらに伏兵があったわけである.つまり,オリンピックである.2026年の冬季五輪に札幌が手を上げたわけであるが,冬季五輪は元々候補が少なく,昨今の開催費の負担に耐えられない都市が多くなったことが重なって,東京五輪6年後であるにもかかわらずあっさり札幌に決まった.そういえば前回の札幌五輪も東京五輪から8年しか経っていなかった.そう,オリンピック開催が決まったことでさらに全線開業が前倒しになったわけである.全線開業は2025年の秋であった.
札幌-東京間は1000km以上もあり,新幹線といえども航空からか客を奪うことが難しく,経済合理性の観点では函館延伸も札幌全線開業両方とも,航空と同程度のサービスレベルを提供するのがやっとで交通サービス水準を向上させたとは言えず,厳しい状況であった.そこで,函館延伸には「背骨」理論でPRし,全線開業にはオリンピックを持ってくるという作戦だったわけであるが,開業しても所要時間が長いことは否定できなかった.そこでいくつかの案が検討され,実際に実行された.
一つ目は速度の向上であった.新幹線電車そのものは350km/h運転できるようにブレーキ系統を中心に改良が行われ,同時に盛岡以北の整備新幹線区間の260km/h運転の縛りを緩めることが検討された.結局,盛岡以南と同レベルの騒音ならば260km/h運転にこだわらないということになり,首都圏を脱したあたりから札幌までの350km/h運転が実現することになった.
もう一箇所,問題があった.青函トンネルである.在来線の貨物列車が走っていたため,新幹線が高速走行しているとすれ違い時に貨物列車が風圧で転倒する危険があったため,新幹線は140km/h運転になっていた(まぁ,もっとも,貨物が無くても連続勾配があるので,昔の新幹線電車だとブレーキの関係で160km/h運転程度が見込まれていたわけだが).当初は信号システムの改良とダイヤの調整で一部列車が260km/h運転していたが,大半の列車が減速運転せざるを得ず,オリンピックを機に北海道と本州の間の交流が活発化したため抜本的改善が望まれるようになった.
そこで,もう一本トンネルを掘る案が出てきたが長大海底トンネルは工費が高い.そこで,新型の新幹線電車が走ることを前提に勾配をきつくして,トンネル延長を短くすることになった.30‰勾配が採用されたため,トンネル延長は元の54kmから35km程度へと大幅に短縮された.元のトンネルについても在来線貨物列車だけ走らせるだけではもったいないという話になり,新幹線用の広軌線路を使用してカートレインも運行されることになった.これに伴い旧トンネルは国道指定されることになり,旧トンネルを道路財源で買い取った形となってそれが新トンネルの建設財源になっている.今や青函旧トンネルは国道5号の一部であり,国道5号の起点は函館から青森に移された.新幹線が通れるトンネルが2本になったことで夜間運転が実現し,新幹線を経由する北海道行き夜行便が復活した.
北海道新幹線は計画としては旭川終点であるが,さすがにフル規格は厳しいという話になり,道内幹線鉄道計画は大幅に見直された.主要路線は新幹線と直通する三線軌でミニ新幹線が函館以北の北海道新幹線と直通し.三線軌でない区間は寒冷地仕様のFGTが直通している.こうして道内幹線鉄道網は一新された.
・・・と,ここまで見たところで目が覚めた.
















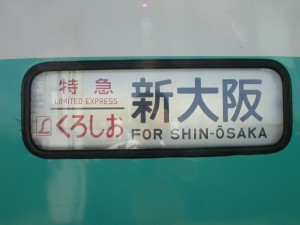












 Views Today : 49
Views Today : 49 Views Last 7 days : 3123
Views Last 7 days : 3123 Views Last 30 days : 12246
Views Last 30 days : 12246